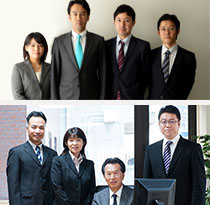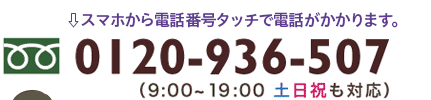こんにちは。ひかり司法書士法人の岡島です。
昨年から民法改正が親族、相続法で随時適用されています。今回はその中で、遺留分に関する改正についてお話したいと思います。
まずはじめに、遺留分とは何かということですが、簡単にいうと法定相続人が財産を取得できる最低限度の割合のことです。
例えば、父親、母親、息子2人の4人家族の場合、仮に父親が亡くなったとすると、配偶者である母親の遺留分は法定相続分1/2×1/2で1/4になります。
息子それぞれの遺留分は法定相続分1/4×1/2で1/8となります。遺産が4000万円だとすると、母親は最低でも1000万円、息子は500万円、遺産の中からもらう権利があるのです。
ちなみに、この遺留分は被相続人、上記例の父親の兄弟姉妹にはありません。
ですので、仮にこの例の夫婦に息子がいなかった場合の法定相続人は配偶者である母親と被相続人である父親の兄弟姉妹ですが、生前に被相続人が配偶者に財産を相続させるという旨の内容の遺言を残していた場合、兄弟姉妹には遺留分がないので、配偶者に対して持ち分の権利を主張することはできません。
では、改正点に関してお話していきます。改正によって何が変わるのでしょうか。
1 遺留分の金銭債権化
遺留分を侵害された場合の権利内容が変わります。
今の民法では「遺留分減殺請求権」という権利です。この権利は被相続人が第三者に贈与などをした場合で、相続人がその贈与を受けた者から、自分がもらえる最低限度の部分を取り戻すための権利です。
原則、現物返還の効力が生じ、遺留分を侵害している限度で贈与の効力を取り消すというものでした。
ですので、権利を行使しても贈与された不動産などは全てが取り戻せるわけではなく、贈与を受けた者との共有となってしまうのです。
今回の改正で、現在の遺留分減殺請求権から「遺留分侵害請求権」へと名称を変え、この侵害請求により金銭債権のみが発生するようになりました。
これにより権利を行使した場合の効果が変わり、贈与を受けた者と共有状態となってしまう問題が解消されます。なぜなら、遺留分侵害請求権は、贈与などを取り消すのではなく、相続人の遺留分の割合の分だけ金銭の請求のみができるという権利だからです。
贈与された不動産などの権利はそのままで、相続人の最低限度の権利である遺留分はお金で精算しましょうという趣旨です。
2 遺留分侵害の対象期間が相続開始の10年間に限定
今の民法では、遺留分の基礎財産(相続人の遺留分を計算するにあたって、計算の対象になる財産)に含める財産の期間に制限はなく、相続開始前にされた相続人への贈与は、何年前であろうが遺留分を侵害しうる財産の移転であり、基礎財産の計算に算入されてしまうのです。
改正後は相続人に対する贈与は、相続開始前10年間にされた贈与に限り基礎財産に算入されます。
よって仮に15年前に被相続人が相続人に贈与していた場合は、その贈与された分は計算に加えられず、取り戻されることがなくなるのです。
上記2点の改正点から、今後事業承継などがやり易くなります。
創業者である父親と息子2人というケースで、生前に父親が事業資産を全て長男に相続させるという遺言を残したとします。
この場合、後継者ではない次男には遺留分として1/4の権利があるので、遺留分減殺請求権を行使されてしまうと、長男3/4、次男1/4という共有状態となり、創業者亡きあとの経営がスムーズにいかなくなる不安がありました。
しかし、今回の改正により、遺留分減殺請求権は金銭債権を請求するのみの遺留分侵害請求権となったために、長男は次男の1/4の部分を金銭で解決し、事業資産である会社不動産や自社株を維持できるようになるのです。
また、遺留分を計算する基礎財産にかかる贈与は相続開始前の10年間に限定されたので、早期に長男に贈与しておけば、10年が経過することで、遺留分の問題が生じなくなります。
今回ご紹介した遺留分に関する改正が適用されるのは2019年の7月1日以降にお亡くなりになった方の相続に関してです。
この記事がこれからこの制度を利用される方のお役に立てて頂ければと思います。