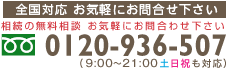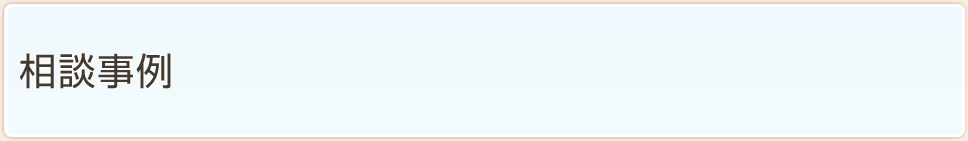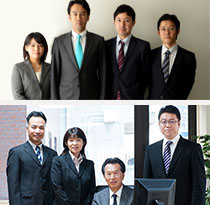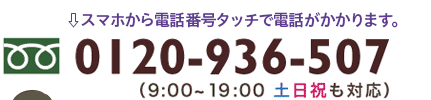皆さんこんにちは。ひかり司法書士法人の岡島です。相続のご相談の際に頻繁にお尋ねされるのが、相続財産の分け方(遺産分割の内容)についてです。
「法定相続分のまま分けたいが問題ないか?」「父が亡くなり、相続人は母と長男、次男だが、やはり母が全て相続するのが一般的なのか?」「不動産を売却し、現金化したものを分けることはできるのか?」など様々です。
今回は遺産分割の方法についてお話したいと思います。現金や預金に関しては法定相続分やその他の割合などで分けやすい財産ですので、今回お話するのは不動産に関しての分け方(遺産分割)とさせて頂きます。
不動産の遺産分割の方法には3つの種類があります。それは「現物分割」「代償分割」「換価分割」といいます。
- 現物分割
現物分割とは、不動産をそのままの形で引き継ぐ方法です。土地や建物を残された配偶者などの特定の相続人が1人で相続したり、土地を法定相続分の割合と同じ割合で「分筆」して各相続人が取得したりします。「分筆」とは、一筆の土地をいくつかの部分に分けてそれぞれ登記して別の不動産にすることです。(※建物は分筆できません。)不動産の「相続登記」は司法書士が行いますが、この「分筆」の登記は土地家屋調査士が行います。「分筆」を行う場合、隣接するすべての土地との境界を明示する必要がありますので、相続登記だけの場合よりも時間や費用が多くかかります。現物分割は1人の相続人がそのまま不動産を取得するということで手続きが簡単になりますが、相続人間で不公平になりやすい点が問題です。 - 代償分割
代償分割とは、不動産を1人の相続人が取得し、他の相続人に代償金を支払って解決する分け方です。例えば、3000万円の不動産が相続財産で、3人の子供が相続する場合、長男が不動産を相続し、兄弟2人にそれぞれ1000万円ずつの代償金を支払って解決します。代償分割は現物分割と違い、代償金が支払われるので他の相続人からの不満が出にくい分け方です。また分筆できない土地でも建物でも公平に分割できることがメリットです。ただし、代償分割するときには、不動産の「評価」が必要です。評価方法にもいくつか種類があるので、相続人間でどの評価方法を適用するかということで - 換価分割
換価分割とは、不動産を売却して売却金を相続人間で分け合う方法です。相続人が協力して不動産を売り、諸経費を差し引き、手元に残った金額を分配します。換価分割の場合、不動産を売却するので「評価」の必要はありません。ですので、どの評価方法を適用するかで相続人たちがもめるリスクがなくなります。
ただし、相続した不動産が必ずしも売却できるとは限りません。また、売却できたとしても諸経費等を差し引いて手元に残る現金が思ったより少ないということもあり得ます。
3つの方法にはメリット、デメリットがそれぞれあります。これが正解というものはありません。
最終的には相続人間で合意する必要がりますので、なるべく各相続人が納得しやすい形に近づけていくしかありません。不動産の内容、相続人間の状況などに応じて、どの方法で遺産分割するのがよいのか検討していくべきでしょう。今回の記事がその参考になれば幸いです。
こんにちは
司法書士の安田です。
今回は、「土地の名義変更を自分でする」についてお話をしたいと思います。
2024年を目途に相続による土地の名義変更の義務化がスタートします。
現在は、相続による土地の名義変更は義務ではありませんので、その時になって慌てないようにできるうちにやってしまいましょう。
相続が発生するとやらなければいけない手続きがたくさんあります。
大きなものでいうと、土地の名義変更、相続税申告などがあり、小さいものでいくと故人の運転免許証の返納や世帯主の変更届などがあります。
役所で申立てするだけの手続きもありますし、必要な書類を揃えて申請書をしっかり作ってという手続きもあります。
その中でも土地の名義変更は、難しい部類に入ると思います。
何が土地の名義変更を難しくしているのか。
私の経験上、土地の名義変更を難しくしているのは次の3つだと考えます。
- 必要な戸籍の収集
- 遺産分割協議書の作成
- 法務局へ提出する申請書の作成
逆にいえばこれら3つさえクリアできれば、そこまで名義変更は難しくないです。
そこで上記3つの作業のポイントを簡単にお伝えします。
まず①必要な戸籍収集です。
戸籍は最近のものはパソコンで作られていて読みやすいですが、古いものだと手書きで書かれており、読むだけでも大変で、そこから必要な情報を読み解くのは慣れていないと中々できません。ですので、集める際は、読み慣れている役所の方に読んでもらいましょう。
つまり、役所へ行くときには、担当の方へ、「相続手続きで使うので出生から死亡までの戸籍をください」と伝えましょう。
そうすれば、役所の方が必要な分をすべて持ってきてくださいます。また戸籍は、本籍地のある役所でしかとれないので、本籍地が変わっている場合、一つの役所で取り切れないこともあります。その場合も次はどこの役所に行けばいいですかと担当の方に聞けば教えてくださいます。次の役所でも同じようにすれば最終的に揃います。
揃ったものを法務局や銀行などに提出して、万一足りないと言われた場合、足りない部分はどこかをその担当者に聞いて、それをまた役所に取りに行けばいいのです。
これで戸籍がややこしくてよくわからなくても問題ありません。
次に②遺産分割協議書の作成です。
遺産分割協議書を必ず作成しなければいけない場合というのは、不動産の名義変更をする場合と相続税申告が必要な場合です。
すべての方が不動産を持っているわけではないですし、相続税申告が必要なわけでもありません。
まずは、不動産の名義変更が必要か、相続税申告が必要かどうかを確認し、必要なければ作らなくても構いません。預金があったとしても遺産分割協議書を作らずに銀行にある相続手続きの書類にハンコを押せば手続きは可能です。
しかし、不動産の名義変更が必要な場合は、遺産分割協議書を作らなければいけません。
その場合は、不動産のことだけを書けばいいのです。
被相続人の情報、不動産の情報、不動産をだれが相続することになったか、これが書いてあれば、遺産分割協議書としては成立します。インターネットにもひな型が載っておりますし、法務局にもひな型が置いてあるので、参考になさってください。
最後に③法務局へ提出する申請書の作成です。
こちらもインターネットなどでひな型が載っておりますが、一番いいのは、法務局へ行って無料の登記相談を受けることです。提出する法務局の方が相談を受けてくださるので、一番確実です。申請書の書き方や必要な書類などを教えてくれます。
以上は、土地の名義変更に必要な手続きの中で特に難しい部分について、お話しました。
やっぱり難しいから、お願いしたいという方や別に難しくはないけど面倒だからお願いしたいという方がいらっしゃったら、ぜひご相談ください。
皆さんこんにちは。ひかり司法書士法人の岡島です。今回は遺言についてお話させて頂きます。これまで一般的な遺言の方法として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」についてはブログ等でお話したことがありますが、今回は通常とは違った特殊な遺言をご紹介致します。
それは「危急時遺言」と呼ばれるものです。遺言には普通方式と特別方式という2つの方式がありますが、この「危急時遺言」は特別方式によるものの1つです。遺言者に死亡の危急が迫り署名押印ができない状態の場合に、口頭で遺言を残し、証人が代わりに書名化する遺言の方式です。
①危急時遺言の要件
- 証人3人以上の立ち会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授する。
- 口授(口が聞けない方の場合は、通訳人の通訳)を受けた証人がそれを筆記する。
- 口授を受けた証人が筆記した内容を、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、または閲覧する。
- 各証人が筆記の正確なことを承認した後、遺言書に署名押印する。
②家庭裁判所による確認
危急時遺言による遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求し、遺言の確認をする必要があります。家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができません。
③危急時遺言の失効
遺言者が普通方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月生存するとき、危急時遺言は無効となります。
このように「危急時遺言」は一般的に馴染みのある「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」より作成のハードルがかなり上がります。実務として取り扱うこともほとんどありません。
また、本人の状況にも左右されるためその作成が完了するかも不確定です。このような特殊な遺言の方式によることなく、早いうちから遺言書を準備されることを強くおすすめ致します。
遺言は元気なうちにゆっくり時間をかけ、熟慮を重ねて作成しようと思われている方。逆に考えるのも面倒なので作成を先延ばしにされている方。そんな方はぜひ弊社の発信している情報にアクセスをお願いします!
弊社で掲載している自筆証書作成に関する記事やYouTubeにアップしている動画をご活用ください!チャンネル登録はこちら
最近よく、相続登記の義務化の話をききます。
私が司法書士をしているからというのもありますが、もう近い将来、法律で相続登記が義務化され、放置しておくと罰金という制度が始まります。
それに隠れてではないですが、住所変更登記の義務化もスタートするようです。
住所変更登記のことは正式には登記名義人住所変更登記といい、司法書士はこれを略して名変と呼びます。今まで住所変更登記は、売買するときや、担保設定するときなど、何かのついでにすることがほとんどで住所変更したから登記も変えなければと思う人は、少数派だったと思います。
ただ、住所変更した後の住民票の保存期限は5年しかないですし、他に住所を証明する戸籍の附票も、除籍になってから5年で破棄されるため、何回か住所変更をしていたり、しばらく放置していたりすると簡単に住所変更登記をするための、登記上の住所と現在の住所の沿革をつけるための証明書をつけることができなくなります。
例えば、甲さんがAという住所にいた時に、土地を買って登記をすると登記上の住所はAとなります。
その後、甲さんが、A→B→C→Dと住所を変えるも、登記の住所を変更していない場合、登記上の住所はAですが、Aさんの印鑑証明書の住所はDとなります。
売買による移転登記をするには、印鑑証明書の住所と登記上の住所が一致していないといけないので、所有権移転登記の前提として名変、つまり登記名義人住所変更登記を申請するのですが、その際に、甲さんは、Dの住所の住民票、Cの住所の住民票除票、Bの住所の住民票除票、Aの住所の住民票除票を法務局に提出しなければなりません。
しかし、住民票除票の保存期間(取得することができる期間)は除票になったあと5年しかありません。つまり、AからBに住所変更したのが5年以上前の場合、必要な書類を準備することができなくなります。これは実務上、珍しいことではなく、割とよくあることで、代替手段を使って名変することは可能ですが、場合によっては難しいこともあります。
こういった事態を防ぐために、住所変更登記の義務化はとてもいいことだと思います。
しかし、たかが住所変更登記といっても申請書を作って法務局へ変更する必要がありますし、不動産をたくさんもっている方は、一度住所を変えただけで各不動産の管轄すべてに申請をしなければならないので、所有者の方には負担が増える話になります。
これも時代の流れで仕方のないことなのかもしれませんが、我々ひかり司法書士法人でお力になれることがあれば何なりとご相談ください。

③家族でのお話合い
家族信託を実現するためには、本人だけでなく家族の協力や情報共有が不可欠です。事前に行って頂く話し合いで、何を念頭におきながら話したらよいのかを下記にまとめました。全てではありませんが、下記の事項が固まれば家族信託の核となる部分はできあがります。
1.信託目的の趣旨、信託目的の対象者・対象財産は何か
- ・委託者(財産を託す人)の目的は、生前の本人のためか、特定の家族の生涯のためか、それともいずれもか
- ・家業、事業の承継か、後継者は決まっているか
- ・財産は何か、特定できる問題のない財産か
2.生前の受益者、その給付内容・程度その他の制約
- ・今からの受益者は誰か
- ・生活、療養看護のためか、その他の要素も含めるか、給付内容、範囲、規模は
3.委託者死亡後の受益者、その給付内容、その他の制約等
- ・委託者死亡後の受益者は誰か
- ・生活、療養看護のためか、施設入所、その他の要素もふくめるか、給付内容、範囲、規模は、いつ取得させるか
- ・税負担の程度、その資金源は
4.遺したい財産があるか、残ればどうするか
- ・どこに、誰に、何を渡したいか
- ・託終了時の残余財産の帰属先は誰か
5.受託者(託される人)を誰にするか、費用負担はどの程度か
- ・最も信頼できる者、理解者は誰か、その関係は
- ・専門家の支援か、監督が必要か
上記の点を意識してお話して頂いて、家族信託で何を実現されたいか、また本当に実現可能なのかを検討していく必要があります。
④必要書類の準備、収集
下記の資料が公正証書による契約書作成までに必要なものとなります。
- ・本人確認資料
運転免許証、パスポート、マイナンバーなど委託者、受託者の方のもの
- ・印鑑証明書
委託者(受益者)と受託者のもので、発行されて3ヶ月以内のもの。
- ・ご実印
- ・戸籍謄本
家族関係を証明するために必要となります。
- ・住民票
委託者、受託者だけでなく、当事者の方(受益者や信託監督人など)のもの全て。
- ・信託財産に関する資料
不動産(土地や建物)を信託財産とする場合は、登記事項証明書(俗にいう登記簿)と固定資産税の評価証明書や課税明細書が必要です。
契約書作成後、不動産の信託登記の際に必要となる書類
- ・権利証(登記済証、登記識別情報通知)
- ・委託者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- ・受託者の住民票
- ・委託者の実印
- ・受託者の認印
- ・委託者、受託者の本人確認書類(運転免許証等)
第3回では、家族のお話合いで何を注意して進めるか、その後に何を準備しておく必要があるのかについて詳しくお話させて頂きました。次回の第4回では⑤信託契約書の作成、⑥金融機関、公証役場との打ち合わせの2つについて掘り下げていきます。
相続登記をご自身でやってみよう!という方に向けた内容になります。
今回は、遺言書がある場合の相続登記のお話です。
お亡くなりになられた方が遺言書を作成されていた場合、遺言書の内容に沿って不動産の相続登記を行う事になります。
相続登記申請の際には、登記申請書の他に様々な添付書類を法務局へ提出する必要があります。
【一般的な相続登記の添付書類】
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
遺言書がある場合には、遺産分割協議書を作成する必要がありません。
また、その他の添付書類も変わってきます。
遺言書には大きく分けて次の二つがあります。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
まず、公正証書遺言ですが、こちらはお亡くなりになられた方が、生前に公証人役場にて作成された遺言書です。
こちらがある場合、相続登記手続きをかなり簡便に行う事が出来ます。
【公正証書遺言がある場合の相続登記添付書類】
- 公正証書遺言
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍
- 相続人の戸籍
- 相続人の住民票
一般的な相続登記との大きな違いとしては、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍を収集する必要がない事と、遺産分割協議書を添付する必要がないという2点になります。
次に、自筆証書遺言がある場合の相続登記添付書類です。
自筆証書遺言とは、お亡くなりになられた方が、生前に全文を自筆で書いた遺言書です。
【自筆証書遺言がある場合の相続登記添付書類】
- 自筆証書遺言(検認済)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍
- 相続人の戸籍
- 相続人の住民票
一見すると、公正証書遺言の場合とそんなに変わりません。
しかし、自筆証書遺言を登記申請に使用するためには、家庭裁判所で遺言書の「検認」を受ける必要があります。
検認とは、裁判所で遺言書の内容や状態を確認してもらう手続きです。検認をしなければ遺言書によって不動産の相続登記をすることができません。
家庭裁判所で検認を行うためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍等の全ての戸籍を収集して申し立てを行い、相続人が家庭裁判所に出頭するなどの中々の手間がかかってきます。検認が完了するまでの期間も1か月程度かかってしまいます。
自筆証書遺言は、簡易に作ることが出来ますが、その代わり実際に手続きに使用するためには手間がかかる事に注意が必要になります。
また、自筆証書遺言は法律上、非常に厳格な方式が定められており、方式に違反した遺言は無効となってしまいます。
無効の遺言書は、当然遺言者がお亡くなりになった後からでは修正することが出来ませんので、せっかく遺言書を書いたにも関わらず全く意味の無いものとなってしまうこともあります。
そのため遺言書を残される場合は、費用はかかりますが、公証人役場で公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。
公正証書遺言の作成のご相談は、ひかり相続手続きサポーターへお問合せください。

こんにちは。ひかり司法書士法人の岡島です。ハウツー 家族信託の第2回となります。
今回は前回ご説明した大まかな流れのなかの
①面談・ヒアリング、②プランの提案について詳しくお話していきます。
信託相談の面談・ヒアリング
まず、信託に関する簡単なご説明を致します。聞きなれないワードも多いですし、全て説明しその場で全てご理解頂くのは難しいので、大枠を掴んでもらうことが目的です。「委託者」「受託者」「受益者」の役割を中心にご説明し、「信託」によって何ができるのかをお話します。
また、信託契約を設計する上で必要な情報をお聞きします。まずは保有資産の概要、家族関係、本人及び家族のご希望をお聞きし、信託によってどんなことがしたいのか、何を望まれているのかを把握致します。もしかするとこの最初の段階で、遺言や生前贈与、任意後見を合わせて考えておかれた方がよいケースもありますし、逆に信託を設定せずともそれらの方法でご希望がかなう場合もあります。ですので、どんな方法がいいのか当てはめる前に、相談者の現在の状況や家族関係を踏まえて、広くお考えをお聞きします。
お話をお聞きするなかで、今回のご相談の核となる目的が見えてきます。老後の財産管理、あるいは円満な財産処分、資産承継、相続税対策など何を望まれ何をゴールにされたいのか。
それが分かれば、類似する信託の事例をご紹介させて頂いたり、信託契約を設定した場合のメリットやデメリットをご説明できたりします。そして相談者の方にあったプランの提案に進んでいけるのです。
※捕捉
信託検討時に用意して頂きたい資料
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産税課税明細書
- 委託者の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、身分証のコピー
- 受託者の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、身分証のコピー
プランの提案、費用感や期間のご説明
ひとくちに家族信託といっても、その中身は以下のように様々です。
- 資産の確実な二次承継・移転
- 残された配偶者の居住・生活資金を確保
- 自身の判断能力低下に備え、家族の生活が安定するようにしたい
- 遺産分割協議をせずに相続手続を素早く簡単にしたい。
- 成年後見制度も利用しつつ、家族のためにも財産が活用できるようにしたい。
- 自社株、先祖からの不動産を維持し、議決権行使を円滑にし、今後の相続による家産・事業承継、分散を避けるとともに、他の相続人の生活を安定させたい。
面談・ヒアリングでお聞きした情報を基に、ご要望にそった最適なプランを検討させていただきます。また、かかってくる費用や期間なども大まかにご説明します。もちろん、プランによって大きく変わるので、正確な金額をご提示するわけではありません。ただ、信託を行うにはある程度のまとまったコストがかかるということをご理解頂くためです。
信託を進める上では、相談者の想いがどういったものかが重要ですが、他のご家族の理解と協力も不可欠です。なので、次回ご説明する家族での話し合いが必要となってきます。
第3回では、③家族での話し合い ④必要書類の収集に関して詳しくご説明いたします。
今回は、「長期間相続登記がされていないことの通知」についてのお話です。
新しく始まった制度ですが、先日この通知書が届いたお客様より相談を受ける機会がありました。
どういった制度かというと、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づいて、長期間にわたって相続登記が行われていない土地の登記名義人の法定相続人を法務局が調査し、その中の任意の1名に、「通知書」を送る制度になります。
(HPより引用)
土地の所有者が亡くなった後に、相続人に名義を変更するための相続登記が長期間にわたって行われていないため、現在の所有者が不明となっている土地が増えていることが社会問題となっています。
このような土地を解消するため、法務局が長期間にわたって相続登記が行われていない土地を調査し、その土地の所有者の法定相続人を探索する作業を実施しています。
法務局は、特別措置法に基づいて、土地所有者の死亡の有無や法定相続人を調査するために職務上の権限で戸籍謄本等を請求して取得することが認められています。
その調査に基づいて、法定相続人となる方のうちの1名の方に対して、この機会に相続の登記申請を行ってはどうですか?といった通知書を送付しています。
通知書は、複数いる相続人のうち1名にしか届きません。相続人のうち、誰に通知書を発送するかは、不動産の近郊に居住されている方や、親等的に近い方など、所有者を知っていそうと思われる方を選んで、通知書を送付されているようです。
また登記簿には、長期間相続登記未了である旨の付記登記がなされます。この付記登記は相続登記が行われることによって抹消されます。
相続登記は現在のところ義務ではありません。しかし、相続登記を行わないまま長期間放置していると、様々なデメリットが生じるおそれがあります。
【相続登記を放置したデメリット】
- 相続登記を行わず放置している間に、新たな相続が発生すると法定相続人が増えて権利関係が複雑になっていく。
- 法定相続人が増えると法定相続人の調査に時間がかかったり、相続登記を行うための費用が高額となるおそれがある。
- 相続登記が行われていない場合は、権利関係が確定していないので、不動産の処分をすることができない。
- 相続登記が行われていない場合には、災害が発生時などに、所有者の特定が困難なため復旧作業の妨げになるなどの問題が発生する。
上記のように、相続登記を行わなければ様々なデメリットが生じてしまいます。
そのため、通知書が届いた場合、これを機会に相続登記することを考えてはいかがでしょうか?
この通知を行う際に、法務局が職権で相続情報を調査されているので、基本的に戸籍収集の作業が不要になります。
膨大な量の戸籍収集を行う必要がないので、通常よりも費用を抑えて相続登記の申請を行う事ができます。
通知書が届いた方は、一度ひかり司法書士法人にご相談ください。
司法書士の安田です。
今回の記事は、相続登記の義務化についてです。
2月11日付けの日経新聞にて土地登記を相続発生後3年以内にしなければ過料を科すという内容で法制審議会は検討しているようです。
相続登記の義務化については、土地所有者不明問題や空家問題などから、数年前から検討されてきて、施工まであと少しといったところまで来ているようです。
既に、数十年相続登記がなされていない土地について、法務局が独自に調査して、相続人宛てに相続登記を促す通知がいくという制度は始まっているようで、先日初めてその通知が届いたという方から相談を受けました。
当初、相続登記の義務化及び懈怠については過料という話を聞いたときは、法律上そのように定めても実際には、過料を科すケースはそこまで多くないのではないかと考えておりました。土地や建物の現況を公示する表示登記については、以前から登記義務が課されておりますが、未登記の建物があっても過料が科せられるケースはほとんどありませんでした。
ただ、上記のような通知制度も既に始まっており、法務局の本気度が伺えるので、3年以上登記をしなければ、一律に過料を科せられるようになるのではとも思います。
このように、相続登記の義務化は今後避けられないものだと思います。我々司法書士は唯一の登記申請代理ができる資格業として、今まで以上に、不動産登記とお客様の橋渡しができるようになれればと思います。
ただ、登記申請の義務化となれば、手続きの簡素化(既に、遺言書の保管制度や法定相続証明情報制度などが始まっています)や相談窓口(現在も法務局でやっておりますが)の増加などを国策として進めていくことになり、もはや司法書士に依頼しなくても相続登記ができる状況になるのではないかという心配もあります。
まだ、義務化についての法律の施行も決まっておりませんし、今後どうなるかわかりませんが、相続登記だけでなく、相続という問題に取り組む一番身近な専門家として、これからもお役に立てるように頑張っていきたいと思います。
相続、遺言書、後見などでお困りのことがあればお気軽にひかり司法書士法人までお問合せください。
司法書士の安田です。
みなさんは相続税についてどんなイメージをお持ちですか。
お金持ちがかかるもの、すごく大変そう、もしかしたら自分は相続税がかかるかもしれないけど、まだ先の話なのでその時に考えよう。
これらはすべてその通りだと思います。
相続税の相談ができるのはもちろん税理士さんなのですが、相続手続きについて相談にお越し頂いた方で、相続税がかかることが分かり税理士さんと一緒に相談を何度も受けた経験から、司法書士が語る相続税について書きたいと思います。
冒頭の、相続税のイメージでお金持ちがかかるものと記載しましたが、相続税がかかる人の割合は国税庁HPによれば約8%とのことです。92%の人はかからないとなるとイメージ通り、お金持ちがかかるものというのはあながち間違いではありません。
ちなみに平成27年の税制改正前は約4%でした。
次にすごく大変そうと記載しましたが、私が税理士さんとお客様とのやり取りをみてる限りでは”すごく大変そうです。”
業務完了後の資料をお客様に返却されているのをみたりしますが、ファイルの量が我々とは比べものにならないです。
登記の変更を自分でしたという話はたまに聞きますが、相続税申告を自分でしましたという話はあまり聞きません。
相続税申告の業務は、受任してから、完了まで3~4か月程度がかかります。相続税申告の期限は、被相続人が亡くなってから10か月ですのであまりゆっくりしていると期限がきてしまいますので、注意が必要です。
わたしが相続税について特に怖いと思うのは以下の3点です。
- 単純に税率が高い
相続税の税率が遺産の金額があがればあがるほど税率があがっていきます。
例えば基礎控除を除いた遺産が1億であれば税率は30%となります。
つまり何もしていなくても3000万円を相続が発生したというだけで、税金として納めなければならないのです。
基礎控除を除いた遺産が3億円以下だと45%となり、通常の所得の方一生かけて納めるくらいの税金を、一気に納めなければならないのです。 - 現金が無くても納めなければならない。
これは地主の方や、都会(特に23区)に不動産を持っている方が考えなければならない問題です。私は今、東京の事務所におりますので、当然ながら東京に不動産を持っている方の相談をよく受けますが、23区内の土地の高さは異常です。東京に来る前は主に滋賀県にいたので、不動産の価格の高さに特に驚くのですが、都会にそれなりの大きさの土地を持っていた場合、それだけで基礎控除を超えることもよくあります。その場合、相続税を納めなければならないのですが、原則的に相続税は一括で現金で納めなければなりません。
不動産はあるけど、金融資産がそれほどないという方は、不動産を売却してでも、納税資金を工面しなければなりません。先祖代々の土地や居住している不動産であっても相続を理由にお金に換えなければならないということがあるのです。 - 遺産分割協議がまとまらなくても期限は来る
相続税申告の期限は、上述した通り、被相続人のお亡くなり後、10か月と定められています。10か月は長いようで短く、例えば、遺産分割協議で揉めてしまった場合、決着がつくまで2年くらいかかることもあるとききます。
そのような場合、遺産分割協議が定まっておらず、誰がどの財産を相続するか決まってなくても相続税申告し、納税をしなければ、無申告加算税などのペナルティが課されます。
このように相続は人生において大きなイベントですが、相続税も人生において大きなイベントとなる方もたくさんいらっしゃいます。
ただし、準備をすることで、ある程度対策を取ることはできますし、相続対策は早ければ早いほど選択肢も増えますし、効果も増えます。
ひかり司法書士法人では税理士さんと提携し、上記のようなこわい話にならないようにお手伝いをすることができると思っております。
相続人の方は、親御様になかなか言い出せず、被相続人様は自分の死後の手続きについて考えられないものですが、準備をしておくことで大きく異なりますので、まずは一度お話しにきてみてください。