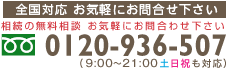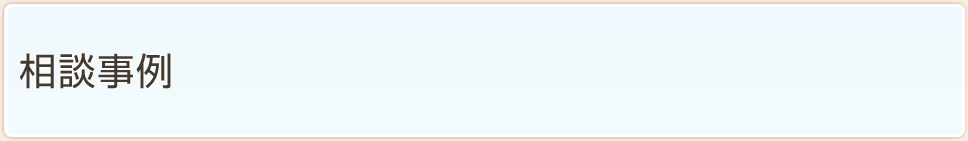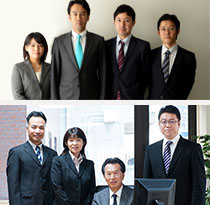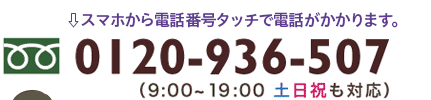こんにちは 測量部の道中です。
今回は地籍調査についてお話しします。
土地所有者様、地籍調査について、ご存知でしょうか?
地籍調査とは、国土調査法に基づき、主に市町村が事業主体となって行います。
地籍とは、「土地に関する戸籍」のことであり、それらを調査することです。
そして一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界を確認し、面積を測量して現地と合致する正確な地図・地積測量図及び登記簿を作成していきます。
なぜ、地籍調査が必要かといえば、現在、登記所に備え付けられている公図は、明治時代の地租改正事業によって作成されたもので、旧土地台帳付属地図であるため、精度は非常に低く、長い年月の経過により旧土地台帳と現地の形状が一致せず、土地の境界や地積が不正確なものがあるため、土地の売買や不動産取引の際、境界紛争等が生じる可能性があります。
そのため、地籍調査を行い、土地の一筆ごとに境界を確認し、精密な測量を行い、精度の高い地図・地積測量図及び登記簿を作成する必要があります。
土地に関するトラブルの話は当事務所でもよく耳にします。
例えば
- 隣が家を建てているが、自分の敷地に越境しているので確認してほしい。
- 家を建てるために隣地との境界に塀を建てようとしたが、境界がわからない。
- 土地を売ろうとしたが正確な面積がわからなかった。
- 土地を購入したが、登記簿の面積と実際に測った面積が違った。
などですが地籍調査を行うことによって精密な地図が作成されることで、土地の位置が特定できるので、上記のような境界に関するトラブルを未然に防ぐことができます。
又、法務局に備え付けられた地積測量図は座標を持つため、境界標が亡失しても座標に基づいて復元が可能であり、災害復旧の迅速化にもつながります。
主に市町村が主体となる地籍調査事業の作業手順としては以下の手順で行われます。
- 事業計画・準備
- 一筆地調査
- 基準点測量
- 立会い
- 立会い後一筆地測量
- 世界測地系による地積測量
- 閲覧・訂正
- 承認・認証
- 行政主体への備え付け・法務局への送付
これらの作業手順を経て、土地が現地と合致した地図や登記簿になり、法務局において登記され公示されます。
今回は行政が主体となって行う地籍調査についての話になりましたが土地や建物の測量に関する疑問点や気になることがある方はお気軽にお問い合わせください。
今回は、突然、家を失ってしまうかもしれないという怖い話をしたいと思います。
あなたの家が建っている土地は誰の名義になっているでしょうか。
自分の名義だよっていう声が沢山聞こえてきそうですが、実は、全ての人がそうとは限らないのです。
建物は自分名義だけど土地は他人名義になっているという人は意外と多いです。
それは、土地を借りて、家を建てている言わば、土地を借りているという状態なのです。
そうか!地主に突然出て行けと言われて、出ていかないといけないくなるのかと思ったあなた、簡単に言えばその通りですが、ちょっと違います。
なぜなら借地人は、借地借家法で守られていて、正当な理由が無いかぎり、出ていく必要はないので、いくら地主でも急に強制的に出て行かすことはできないのです。
借地借家法とは
土地の貸し借りや、住宅の貸し借りには借地借家法という法律が適用されます。
「借地(土地を借りる)」と「借家(家を借りる)」のために規定された法律で、借りる側に強い権利を与え、借主を保護する法律となっています。
「土地を貸したら帰ってこない」という覚悟で土地を貸し出さなければならないと、よく言われているぐらい、借主よりの法律となっています。まぁ住むことは憲法で守られているので当たり前ですが。
時代が変わって地価が上がってくると、地主側からすると、安い地代で貸しているよりは、ビルでも建てたほうが良いとなり、借地人に対して土地を返してとなるわけです。
しかし、簡単には借地人は返してくれません。なぜなら、親の代から借りているなど昔から借りている場合は、当時の価値での地代で借りているので、今の周辺相場からするととんでもなく安く借りられているのです。
ここからが怖い話になります。
不動産にはいろいろな悪い人が関わってきます。最近で言えば地面師ですね。
バブル時代には地上げ屋というのが暗躍しておりました。
地上げ屋とは、建築用地を確保するため、強引な手法による不動産の売買を進めていく人のことです。
その一つが借地人を強制的に出て行かすというものです。地価が上がりそうな土地を買って、借地人を出て行かし、土地を高値で売るというものです。
ではどうやってするのかというと、
まず借地上の建物を壊します。そして建物滅失の申出をします。後は土地を売るなり、ビルを建てるなりするわけです。
借地借家法では、建物を利用することを目的として土地を借りる場合を想定しています。
ですので、借地上の建物が無くなると借地借家法の効力がなくなるわけです。
どうやって建物を壊すかは、ここでは言えませんが、悪いことをする人はよく考えるものです。
壊した後は、通常は建物所有者からする建物滅失登記を、所有者不明として、土地所有者から申出をして、借地借家法の適用となる借地上の建物を滅失するわけです。
これはバブルの話だけでなく、オリンピックや万博で地価が高騰しているので、今でもあることなのです。
ネットで検索すると、借地関係の地上げ事例が出てきます。
住んでいる居宅だけでなく、遠くにある倉庫とかでもあります。遠くにある倉庫は頻繁に行くことはないので、行ってみると無くなっているということもあるのです。
対策としては、家を長期間空き家にしないということと、一番は、地主と良好な関係を続けること、周辺相場より安い地代に関しては、地主と協議し、相場に近づくように努力するなどが挙げられます。
話がそれますが、建物を壊されたら、裁判をしたら良いのでは?というのがありますが建物の賠償請求はできたとしても、土地は返ってこないので、どこかに引っ越さなければいけないのです。住み慣れたところを離れるのは辛いですよね。
法律で守られていると言っても、その権力に溺れないように気を付けなければいけないということです。
人間は一定の権力を持つと、自分を客観的にみることができなくなり、正しい判断ができにくいというのがあります。
自分は守られているから、何をしても良いんだ、自分が正しいのだと思い始めたら要注意です。
まぁそうなってはバイアスが掛かってしまってますので、すでに遅しとなりますが、この記事を読んでいるあなたはまだ大丈夫です。権力に溺れず借地人としての正しい判断をして、地主と良い関係を続けてください。
以上簡単ではありますが、「突然、家を失ってしまうかもしれないという怖い話」をお話しました。
固定資産税評価証明書とは
不動産の「固定資産評価額」を証した書類であり、その年の4月1日から翌年3月31日までの1年間の不動産の固定資産税上の不動産評価額を示すものです。
この評価額は毎年4月1日の新年度から適用され、新しい評価額に基づき固定資産税や都市計画税が計算され、課税通知書又は納税通知書として、不動産の所在地の各市町村から所有者へ郵送されます。
新年度の固定資産評価額を知るには?
固定資産評価額をお知りになりたい場合は以下の2つの方法があります。
- 「納税通知書」に同封された「課税明細書」で確認する
毎年5月~6月頃に市税事務所や市町村から送られてくる固定資産税の納税通知書に同封されている「課税明細書」の記載を見れば、最新の評価額を知るそとができます。課税明細書には記載されている数字が多いですが、見るべきポイントは「価格」あるいは「評価額」という文字です。これらに記載されている数字が、所有されている不動産の固定資産評価額になります。
- 固定資産評価証明書の請求を行う
不動産を管轄する市税事務所や市町村役場では、固定資産評価額だけを証明した「固定資産評価証明書」の手数料(一通300円程度)を支払うことで取得することができます。
単に新年度の評価額が知りたい場合は①の方法で十分でしょう。
手数料を払う必要もありませんし、郵送でお手元(納税義務者の)に届くので、楽に確認することができます。
しかし、郵送で送られるのが5月~6月になる市町村が多いので、早く評価額を知る必要がある場合や登記申請を控えている場合は②の方法を行うことになるでしょう。
登記申請に評価証明書を使う場合の注意点
登記を申請する場合、法務局に納める「登録免許税」を計算するために評価証明書を添付する必要があるのですが、申請する時期で何年度の評価証明書を取得すべきなのかが変わります。
切り替えの基準となるのは「毎年4月1日」です。
ですので、これから登記申請で添付すべき評価証明書の年度は平成31年度となります。
平成30年度のものを取得してしまった、あるいはもともと持たれていたとしても登記申請には使えません。
再度評価証明書を取得する必要があります。また不動産の評価額が変わってしまっている場合は、登録免許税の計算をやり直す必要もあります。※(相続登記の際の税率は、1000分の4 評価額が1000万円の場合 登録免許税は4万円)
これから登記申請、特に相続登記をご自身で行う場合はご注意ください。
戸籍や住民票と違い、固定資産評価証明書は登記申請において最新年度のものが要求されます。
市町村等の窓口で請求される場合は使用目的を窓口の方にお伝えしてから、交付申請書類をご記入されるのが良いかと思います。そうすれば市町村の係りの方が必要な評価証明書の請求方法を教えてくれるはずです。
以上で今回のテーマである固定資産評価証明書についてのお話を終わりたいと思います。
登記申請に関して何かご不明な点がありましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。

先日、新しい元号が発表されましたね。
「令和」
日本古典である万葉集から初めての採用ということで話題になりました。
また、「令」の漢字が日本の元号に使用されるのも初のようです。
今回は、そんな元号と登記のお話です。
不動産の登記記録には登記の年月日や登記原因日付など、「年」を登記事項として記載することが多いのですが、登記記録は年を「西暦」で記載することはできず、全て「元号」にて記載されます。
元号にて記載しなければならない根拠ですが、これは法律(不動産登記法)に書いてあるわけではなくて行政通達による実務上の運用となっています。
実際に不動産登記法では下記のように「年月日」とだけしか規定されておりません。
「不動産登記法第59条 」
権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一 登記の目的
二 申請の受付の年月日及び受付番号
三 登記原因及びその日付
そもそも元号は皇室典範にて規定があったのですが、戦後の日本国憲法制定にあたって皇室典範が改定されたことにより、元号の法的根拠が失われていた時期が続いていました。
しかし官民問わず、昭和という元号がそのまま一般的に使用され続けてきたのです。
そして昭和54年に「元号法」が施行され、元号の法的根拠が復活することになりました。
「元号法」
- 元号は、政令で定める。
- 元号は、皇位の継承があった場合に限り改める。
元号法は、たった2項だけの構成という、極めて短い法律としても有名です。
その元号法が施行された際に、登記及び供託事務の取扱いについての依命通知が出されました。
「昭和54年7月5日民三第3884号・民事局第四課長依命通知」(一部抜粋)
申請書及びその添付書面中の日付の記載として西暦を用いても、登記記録に日付を記入するときは、すべて元号を用いることとする。
そのため登記申請書を西暦で作成したとしても、登記記録には元号にて記載されることになります。
例えば申請書に2019年5月15日売買と記載した場合であっても、登記記録には令和1年5月15日と記載されます。
また、「元年」も登記記録には記載されず、「令和元年」は「令和1年」と登記記録に記載されるようです。こちらは通達とかではなく法務局のシステム上の都合だとか聞いたことがありますが、本当にそれだけの理由なのでしょうかね。
最近では西暦にて契約書等を作成する金融機関も増えてきましたが、どちらかに統一されていないと申請書作成の際に間違えてしまいそうで司法書士としては注意が必要です。
余談になりますが、新元号の「令和」から「西暦」に変換したい場合は、令和に「018(レイワ)」を足して計算すると分かりやすいそうですね。
例)
令和1年+018=西暦2019年
令和5年+018=西暦2023年
以上、元号と登記のお話しでした。

平成30年度も終わり、新元号も発表され、平成最後の年度となりました。
日本では、1月から12月までの1年間と4月から3月までの年度という考え方があります。
不動産に関することでいえば、4月1日から新しい年度の評価証明書を取得することができ、4月以降の不動産の登記の申請に関しては、31年度の固定資産税評価額が課税価格となります。
そして、早いところでは、4月の上旬には、固定資産税の納税通知書が届きます。よって不動産をお持ちの方のところにはこれから、続々と納税通知書が届くことになります。
今回は、この固定資産税の納税通知書についてお話をしたいと思います。
ちなみに固定資産税とは地方税であり、各不動産の所在の市町村が課税主体となります。ただし、東京23区については、区ではなく都が課税しています。。
各市町村及び都によって、納税通知書が送られてくる時期や記載されている情報には違いがあり、すべての市町村にあてはまるわけではありませんが、ある程度、読み取れる内容は決まってきます。
ちなみに固定資産税の納税通知書といいますが、ほとんどの場合、固定資産税と都市計画税の合算した金額を支払っています。単純な計算方法でいくと固定資産税は、評価額の1.4%、都市計画税は評価額の0.3%ですが、実際には評価額から課税標準額を計算して、その課税標準額に税率を掛けることになります。細かい計算については私も詳しくはわかりませんので、割愛致します。
読み取れる内容① 不動産の名義人がわかる。
納税通知書は、基本的には不動産の名義人宛てに届きます。よって、亡くなっている方名義で届く場合、名義変更が出来ていない可能性があります。
その場合は、速やかに相続登記をすることをお勧め致しますので、その際はひかり司法書士法人にご相談ください。なお、確実に現在の不動産の名義を調べるには、最寄りの法務局へいって、登記事項証明書を取得しましょう。登記事項証明書は、法務局へ行けばだれでも全国の物件の所有者を調べることができます。
読み取れる内容② 不動産固定資産税評価額がわかる。
固定資産税納税通知書と同封して、課税明細書が送られてきます。この課税明細書は、評価額や課税標準額などが記載されております。たとえば、不動産の名義変更や相続税の申告など評価額がわからない場合は、役所で評価証明書を取得する必要がありますが、この課税明細書があれば、評価証明書を取得しないで済む場合がほとんどです。また、評価額がわかれば、名義変更の際に必要な登録免許税の計算ができますので、登記手続きの見積書を作成することができます。
読み取れる内容③ 新築建物の軽減額がわかる。
新築建物の場合、3年間(マンションの場合は5年間)は固定資産税が半分となります。さきほどの課税明細書には、軽減されている額などが記載されている場合もありますので、そこから、軽減が終了した後の固定資産税を計算することができます。
読み取れる内容④ 市場価格が大体わかる。
こちらは参考程度ですが、固定資産評価額は公示価格の7割程度といわれており、公示価格とは、土地の取引価格に対しての指標、公共事業用土地取得の価格算定の基準となっています。よって、売却したいと思った時に、評価額から割り戻しをすればどの程度で売れるのか参考になります。ただし、不動産はちょっとしたことで値段が変わりますので、あくまで参考程度にしてください。
いかがでしょうか。
固定資産税の納税通知書がきても納付だけして、あとはどこに行ったからわからないという方も多いのではないでしょうか。
今年度に届いた固定資産税の書類はせめて次年度の分が届くまで、お手元にもっておけば、急に評価額が知りたいとなった時に役所へいかなくてもわかりますので、お手元に保管されることをお勧め致します。