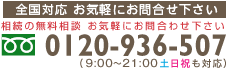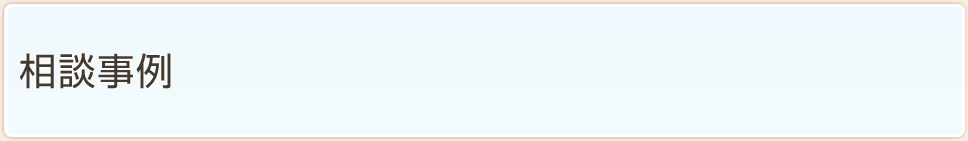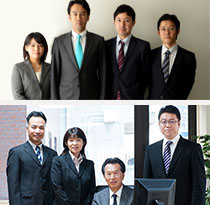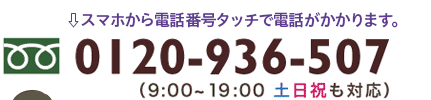皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人の青木です。
今回は2018 年7 月に、相続法の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、2019年7月1日から施行された、「遺産分割前に預貯金を払い戻すことを可能とする制度の創設」についてお話させて頂きます。
簡単に事例を通して説明すると
Aさんの父親(被相続人)、Aさん(長男)、Bさん(次男)の場合
Aさんは父親が死亡したので、父親が持つ銀行口座の金融機関担当者に「父親が死亡したので、預貯金の相続手続きがしたい」と相談したところ、父親の銀行口座が凍結されてしまい、まったく預貯金が引き出せなくなってしまいました。
このような事態は2019年7月1日までのお話です。法律的に理由を説明すると「遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払戻しができない。」と裁判所が判断していたからです。
(平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、 ①相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、 ②共同相続人による単独での払戻しができない)
2019年7月1日からは「遺産分割前に預貯金を払い戻すことを可能とする制度」の適用があるため、Aさんは、遺産分割前にあっても一部預貯金を下すことできるようになります。
上記の制度は具体的に、預貯金債権の額に各人の法定相続分を乗じた額の3分の1まで、各共同相続人が、遺産分割を待たずに預貯金債権を行使できるものとしました。
※民法909条の2 (遺産の分割前における預貯金債権の行使)
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
この規定に基づいて、ある相続人が行使した預貯金債権(銀行預金を引出した金銭等)については、後日の遺産分割においてその者が所得した財産とみなされることとなります。
また、先ほどの事例にあてはめると
(例) 銀行預金 600 万円 →Aさんは100 万円の引き出し可能
※ただし、1 つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円までになります。
この規定は、預貯金の凍結により、葬儀などの費用の支出ができないといった事態を防ぐ趣旨により創設された制度になります。
よって、Aさんはこの制度により全て自腹で父親の葬儀費用等を支払わなくても良くなります。
このように改正された理由としては、1980 年(昭和 55 年)に改正されて以来、日本の相続法は大きな見直しがされてきませんでした。 一方、この間、我が国における平均寿命は延び続け、社会の高齢化が進展するなどの社会経済の変化が生じており、今回の改正では、このような変化に対応するために、相続法に関するルールを大きく見直しを行うことにより国家は少しでも現代社会に適用しやすい法制度を考えているようです。
以上で今回のテーマである遺産分割前に預貯金を払い戻すことを可能とする制度の創設についてのお話を終わりたいと思います。
相続手続きに関して何かご不明な点がありましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。
こんにちは。福岡事務所の長澤です。
認知症や相続対策でよく話題にあがる「成年後見」・「遺言」と、「信託」の話をしようと思います。
認知症と言っても、アルツハイマー型やレビー小体型、脳卒中などによる脳血管性のものなどいくつかの類型があり、症状や進行速度も違いますが、医学的な面はここでは置いておいて、法律的な面から見るとどういうことが起きて、家族や本人が困っているのかを説明します。
まず、認知症になると騙されやすくなる。オレオレ詐欺や悪徳商法などで高齢者がお金をとられたというニュースをよく見かけるかと思います。
以前、「母はお金に余裕があるはずなのにいつもお金が足りないと言ってくる。」という息子からの相談を受けて調べてみると、近所の人にお金を配っていたという事実が発覚したケースもありました。
次に、日常生活で困るという相談が一番多いのが銀行の口座が凍結されることです。
認知症の診断が下りたら自動的に口座が凍結されるわけではありません。窓口で引き出しをするときに行員が認知症に気づいたり、家族が銀行に伝えたり、施設に入るために頭金を引き出すときに認知症だということが銀行側にわかって凍結されたりします。
ただ、これは悪いことではなく、銀行側も認知症になった人が詐欺などにひっかかってしまわないように、財産を保全するために口座のお金を守ることが目的で行っていることです。
しかし、預金があったり、年金の受け取り口座で生活用の口座が使えなくなったりすると困ります。それを防ぐために口座からお金を下ろしておく…ということを考える人もいますが、手元に現金を置いておくと、それこそ悪徳業者の恰好の餌食になるので危険です。
次に、所有する不動産の売却・リフォーム・賃貸などができなくなります。施設入所費用に充てる予定で不動産を売ろうとしても、売却自体ができなくなります。
他にも、株式の取引ができない、遺言が書けない、生命保険に入れないなど色々なことができなくなります。
こういう場合に備える方法として「成年後見」と「信託」があります。
「成年後見」とは、認知症になった人の財産を本人の代わりに管理する後見人という人を選んで、その後見人が口座からお金を下ろしたり、各種契約や手続きを代わりにしたりする制度です。後見人には幅広い代理権が与えられるので、財産のみではなく、施設の入所手続きや、住む場所の賃貸借契約なども代わりに行います。
この「成年後見」には2種類あります。
元気なうちに後見人候補者を自分で選んでおく「任意後見」と、認知症になってしまってから家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」です。
法定後見の場合、家庭裁判所が誰を後見人にするのかを決定するので、子どもが後見人になることもあれば、専門家がなることもあり、子どもと司法書士の2人が後見人になる場合もあります。
現在は司法書士・弁護士・社会福祉士が7割程度後見人になっているため、必ず息子や娘に後見人になってほしい、信用できる人が他にいるのでその人を後見人にしたい、という要望がある場合は、事前に「任意後見」を選択しておく必要があります。
しかし、この後見人は、なんでも本人の代わりにできるわけではありません。投資などのリスクのあるもの、本人の財産が減るような行為は原則としてできません。
認知症の対策としては、「信託」という方法もあります。
これは文字通り、任せたい財産を任せたい人に「信じて託す」制度です。たとえば、賃貸に出している不動産の運用管理、現金、運用中の株式など、自分で何を任せる決めることができます。また、誰に託すかという「任せたい人」も自分で決めます。この任せたい人との間で契約を結ぶのが信託契約です。
信託契約は、通常の契約と同様に、どんな契約にするのかは原則自由に決めることができるので、賃貸不動産の管理だけを任せる、売買して現金に換えて運用してもいいようにする、など柔軟に決めることができます。
「信託」にも「民事信託」「商事信託」と言われる種類などがありますが、これらの区別は様々な見解はあるものの、財産を任される人=受託者が家族などの個人か、信託会社などの信託業者かの違いで分けることができます。
また、相続対策として「遺言」と「信託」の方法が使われることがあり、「遺言」はある程度知名度もあり、ほとんどの方が知られていますが、「信託」はまだまだ知名度が低いです。「信託」を使えば、任せた財産を自分の死んだあともどう使ってほしいか決めておくことができます。
例えば、死んだあとは、長男のために使ってほしいが、長男の死後は、長男の子ではなく、次男のために使ってほしいなど先々のことまで契約内容に入れておくことが可能です。
ただ、「信託」は金銭的価値に見積もりのできる「財産」しか任せることができないという制限もあるため、認知症になったときの住居の決定、ローンや借入の債務は対象にならず、これについては他の制度で補う必要があります。
「成年後見」・「遺言」と「信託」は結局どれがいいのか?という相談がありますが、これらの制度はそれぞれ一長一短があるため、相談者のご家族や希望、財産の状況に合わせて最良の方法を考えていく必要があります。
たとえば、近所に息子が住んでいるが一人暮らしのお爺さんが自宅のみ所有しており、介護が必要になれば自宅を売却して施設に入ることを予定している、というのであれば、元気なうちに「任意後見」で後見人候補者を息子にしておいて、もし、施設入る場合に認知症になっていたら売却手続きを息子にしてもらう、という流れをとればよいと思います。
また、自宅は長男に継いでほしいと考えるのであれば、「遺言」で長男に相続させる方法をとる。ただ、長男には継いでほしいけど長男の嫁には財産がいってほしくない、というのであれば「信託」を使って、長男の死後は別の人のものになるという内容の信託契約を結んでおくという方法も考えられます。
ある財産は長男に運用を任せるけれど、他にも財産があったり、認知症になった場合に自分の入る施設や住居のことも決めたりもしてほしいというのであれば「任意後見」と「遺言」「信託」を併用することもあります。何が一番良いのかは、専門家に相談しながら決めていくことをお勧めします。
ひかり相続手続きサポーターでは、税理士・行政書士・弁護士とも連携し、ワンストップサービスを提供することができる体制が整っていますので、気軽にご相談ください。
家族信託に精通する司法書士「ひかり相続手続きサポーター」が「相続」「遺言」「信託」のこともまとめてサポート
ひかり家族信託サポートサービス
皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人 冨永です。
相続が発生すると相続人全員で協議をおこない、お亡くなりになった方の資産をどのように分けるかを話し合うことになります。
仲良く話し合いできるケースもありますが、中にはスムーズに話し合いがまとまらないケースも沢山ございます。
こんなときに遺言書があれば良かったのにな、と思う事例も多々あります。
そこで、絶対に遺言書を書いておいたほうが良い、代表的なケースを2つだけご紹介いたします。
ケース1「子供のいない夫婦」
子供をつくらず夫婦二人で生活していた場合、男女の平均寿命から考えると夫が先に亡くなることが多いです。
そのときに、夫名義の自宅や預貯金などの財産はどうなるでしょうか?
全部妻のものになるんじゃないの?夫婦二人で築きあげた財産なんだし。
そう思って相談にお越しになられる方も多いのが現状です。
相続が発生すると法律に定められた順位に従って、高順位の人から順番に相続をしていくことになります。
まず配偶者は、常に相続人になります。
第1順位の法定相続人は「子供」です。
第2順位は「親」です。被相続人に子供も孫もいない場合には親が法定相続人になります。
そして、第3順位は「兄弟姉妹」です。
被相続人に子供も親もいない場合には、兄弟姉妹が法定相続人になります。
子供のいない夫婦の夫が先に亡くなった場合、夫の兄弟姉妹も法定相続人になってしまいます。
配偶者の兄弟姉妹と仲良く話し合いができ、妻がすべて相続すると簡単に決まれば良いのですが、最近では親戚間の付き合いも薄れて疎遠になっているケースもよく見かけます。
また、兄弟姉妹が自分にも相続する権利があるのだから取り分をよこせと言ってくることもあるかもしれません。
そんな時に絶大な効力があるのが遺言書です。
「自分が亡くなったら配偶者に全て相続させる。」と書いた遺言書を残しておくだけで、兄弟姉妹と話し合うことも不要になります。
夫婦それぞれが、お互いに上記の遺言書を書いておきましょう。
遺言書は自筆で書いておいても有効なのですが、形式の不備により無効とならないように公正証書遺言で残しておいたほうが良いのは当然です。
万が一遺言書に不備があった場合、お亡くなりになった後では修正することができませんので。
ケース2「前の配偶者との間に子供がいる場合」
これも良くあるケースです。
たとえば父親が再婚し、前妻との間にも子供がいる場合です。
このようなケースでは前妻の子どもとの間で話し合いを行い、遺産をどのように分配するかを決めなければならないのですが、ケース1の配偶者の兄弟姉妹と違い、前妻との子供と一度も会ったことがない場合もあります。
また、相続登記の手続きの際に戸籍を集めていくのですが、その戸籍を見てそこで初めて父親に前妻との子供がいたことを知るケースもございます。
もちろんスムーズに話し合いができる場合もあるかとは思いますが、前妻の子供がこちら側にどのような感情を抱いているか分かりません。
また、自分に権利があると分かれば過大な要求をしてくる可能性もございます。
それに父親は、前妻との子供には多めに財産を分けてあげたいと思っていたかもしれません。
しかし遺言書が無ければ、父親がどんな思いでいたかを知るすべはもう無いのです。
やはりこのケースでも遺言書を残しておけば、とても役にたつことになります。
上記2つは、遺言書を絶対に残しておいたほうが良い代表的なケースですが、その他にも遺言書が役に立つケースは沢山ございます。
残された配偶者、お子様が困ることの無い様に、遺言書を書いておきましょう。
こんにちは。ひかり司法書士法人の岡島です。
今回は最近テレビやニュースなどで取り上げられている「家族信託」について詳しくお話したいと思います。
家族信託とは何か
「財産を信頼できる人に託して、自分や家族を守るために管理してもらう」ことです。
この仕組みを使って高齢者や障碍者のための柔軟な財産管理と円滑な資産承継の両方を実現することができます。まずこの家族信託で重要なキーワードを以下に説明します。
- 信託契約・・・主として老親が子に財産の管理と処分を託すために交わす契約
- 委託者・・・・財産の所有者であり、管理を託す人
- 受託者・・・・託された財産の管理や処分を行う人
- 受益者・・・・信託財産から経済的な家賃収入などの利益をもらう人
- 信託財産の実質的なオーナー
- 信託財産・・・管理・処分を託した財産。不動産・現金・株式が中心
家族信託のポイント
家族信託は信頼できる相手との「契約」であり、契約当事者となる人(親と子など)が契約の目的や効果を理解していないとできません。
ですので、老親の認知症が進んでいるケースではもはや手遅れとなってしまいます。
受託者となる子は、あくまで財産の管理・処分を担うだけで、管理を託した財産は、受益者である親の財産に変わりはありません。
アパートの家賃等の信託財産から得られる利益は、受託者の手元に入ってきますが、契約前と同様、受益者である親の収入であり、従来通り親の確定申告が必要になります。
「管理する権限」と「利益を得る権限」
家族信託を説明するうえで、財産を管理する権限をもっている受託者と、利益を得る権限をもっている受益者の理解が非常に重要ですので、ここで詳しく説明いたします。
あなたが仮にアパートを所有し管理していると思ってください。
新規の入居者から申し込みがあり賃貸借契約を結びます。
この時契約書にサインしハンコを押すのは誰でしょうか?もちろんオーナーであるあなたです。
また、アパートが古くなり修繕が必要となりました。
こんな時、工事業者と契約を結び、ハンコを押すのは誰でしょうか?これもあなたです。
そして、アパート管理が面倒になり建物そのものを売却したくなった時、売買契約書にハンコを押すのもあなたです。
このようにアパートを所有している人は、アパートを自由に管理・処分する権限を持っています。これが「管理する権限」です。
また、アパートに住んでいる入居者は家賃を毎月支払います。これを受け取るのは誰でしょうか?オーナーであるあなたです。
アパートを売却した際の売買代金を受け取るのもあなたです。このように、アパートを所有している人は、アパートから生じた利益を受け取る権利を持っています。これが「利益を得る権限」です。
ものを所有する権利・権限を「所有権」といいます。不動産、金銭、株などの財産を持っている所有者は所有権を持っています。
所有権にはこの「管理する権限」と「利益を得る権限」の両方が備わっておりこれらを分離することはできません。
しかし、この所有権がうまく使えなくなることがあります。
それが認知症になってしまった場合です。
アパートが老朽化し入居者が減ってしまいました。そのためアパートの設備を新しくしたいと思い、工事の契約を結ぶとき、認知症になってしまっている場合、契約書にハンコを押すことができません。判断能力が認められないからです。
それでは成年後見人の制度を利用するのはどうでしょうか?これも難しいでしょう。
成年後見人ができるのは「現状維持」で、アパートの設備を新しくするような工事は投資的な要素があるため、家庭裁判所が認めてくれるかどうかわかりません。
アパートの空室に新規の入居希望の人が来ても、認知症ではあなたは賃貸借契約の契約書にハンコを押せません。成年後見人なら代わりに押すことができますが、成年後見人を家庭裁判所に選任してもらうには時間がかかります。新規の入居者に対して対応ができず、入居者を逃がしてしまうでしょう。
このように代わりに誰かがハンコを押してくれたら、もっと言えば、「管理する権限」を誰かに任せることができたならば。ここで活躍するのが家族信託です。
家族信託なら、「管理する権限」と「利益を得る権限」を分離できる
上記のアパートの例で、自分の子供に信託したとします。信託すると「管理する権限」が法的に子供に移ります。
ですので、新規の入居者と賃貸者契約にハンコを押すのは子供です。
あなたが押す必要がなくなるのです。
アパートの修繕や、売却するのに必要な契約も子供がすべて行えます。なぜならアパートの「管理する権限」を持っているのは子供だからです。
信託後はアパートの事務手続きは子供がすることになり、オーナーであるあなたが認知症になっても成年後見人は不要です。
また、オーナーであるあなたが亡くなってしまっても、相続手続きをすることなく、子供はアパートを管理することができます。
一方で、入居者からの毎月の賃料収入は変わらずオーナーのあなたが受け取ることができます。なぜなら子供に移ったのはアパートを「管理する権限」だけで、「利益を得る権限」はあなたが持ったままだからです。
家族信託が便利なところは、この「利益を得る権限」を自分が指定した人に渡すことができることです。最初は自分、自分が亡くなった後は妻、その後は子供や孫に、というように何代にもわたって指定することができます。
ここで冒頭に説明したキーワードを踏まえながら、信託の仕組みを説明します。
アパートのオーナーであるあなたは「委託者」となります。
アパートを託され管理するのは子供であり「受託者」となります。
「管理する権限」は子供に移ります。
アパートの賃料をもらえる権利である「利益を得る権限」は、「受益者」であるあなたが持ったままです。
この「利益を得る権限」のことを「受益権」といい、この「受益権」を「信託契約」で誰に渡すか、誰に引き継がせるかをあらかじめ決めることができます。
家族信託を利用することで、「管理する権限」と「利益を得る権限」を分離し、それぞれを「受託者」、「受益者」に渡すことができます。これにより、管理は信頼できる人に任せ、収益は自分や家族にわたるように設定することができるのです。
ひかり相続手続きサポーターでは、家族信託に関する専用のホームページ
(https://hikari-souzoku.com/kazokushintaku/)も開設しております。
今回のお話で、家族信託についてもっと知りたい、家族信託が使えるかもと思われた方はぜひ閲覧してみてください。
皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人の青木です。
今回は司法書士の本人確認についてお話させて頂きます。
最近、様々な手続きの際に必要になる本人確認の制度ですが、司法書士の業務でもご依頼を頂いた場合、ご依頼者様の本人確認の手続きを必ず行う必要があります。
大きく2つの本人確認の制度があります、①「司法書士法及び司法書士会会則に基づくもの」、 ②「司法書士の本人確認情報作成のためのもの」です。
まず、1つ目の「司法書士法及び司法書士会会則に基づくもの」に関しては、当事務所本店の京都司法書士会によると、京都司法書士会の会員である司法書士が依頼者様から業務(相談業務を除く。)を受託する際には、依頼者様がご本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、本人であることの確認及び依頼された事務の内容に関する記録を書面又は電磁的記録により作成しなければならないと定められてます。
また、本人確認書類として、下記の証明書のいずれかの提示等が必要になります。
- 運転免許証
- 住民基本台帳カード(顔写真付)
- 旅券
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- その他の公的証明書(顔写真付きで氏名、住所、生年月日の記載があるもの)
- 次の保険などの『被保険者証』or『組合員証』
・国民健康保険 ・健康保険 ・後期高齢者医療保険 ・公務員共済組合 等 - 介護保険の被保険者証
- 国民年金手帳
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳又は戦傷病者手帳
- 印鑑証明書、戸籍謄抄本(戸籍の附票の写し付)、住民票の写し、住民票記載事項証明書 等の官公庁の発行する公的証明書(氏名、住所、生年月日の記載があるもの)
簡単にまとめると、司法書士が登記手続きの依頼を受けた際には、上記の本人確認書類を確認し、依頼者が本人であると確認しなければなりません。
次に、上記とは別の制度の「司法書士の本人確認情報作成のため」の本人確認の説明になります。
そもそも「本人確認情報」とは何か?
まず、売買や贈与、抵当権等の担保設定の登記手続きする際に、登記義務者(不動産の売主、担保提供者等)の登記識別情報や登記済権利証が必要になります。
この登記識別情報や登記済証が紛失などの理由により提供、提出できない場合、司法書士が「本人確認情報」作成し、法務局の手続きを行う登記官が、その内容を相当であると認めたときは、権利書に代わって登記手続きをすることができる制度です。
その「本人確認情報」作成にあたっての本人確認書類は原則、不動産登記規則72条2項に基づき下記の証明書のいずれかの提示等が必要になります。
- 1号書類(顔写真付き公的証明書類)
・運転免許証・個人番号カード(マイナンバーカード)・住民基本台帳カード・旅券・在留カードまたは特別永住者証明書・運転経歴証明書 等
上記書類であれば1つで可能です。 - 2号書類(顔写真のない公的証明書類)
・国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証・健康保険日雇特例被保険者手帳・国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証・国民年金手帳・児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(氏名、住所、生年月日の記載のあるもの)
上記2号書類については2つ以上が必要です。 - 3号書類
2号書類のうちいずれか1つ以上と下記のものが加えて必要になります。官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか1つ以上
※官公庁から発行・発給された書類に準ずるものの具体例の一部
・私立学校の学生証(顔写真付き)・社員証(顔写真付き)・宅地建物取引士証
上記1号書類、2号書類及び有効期間、期限のある3号書類については、司法書士(資格者代理人)が提示を受ける日において、有効なものに限ります。
簡単にまとめると、登記手続きで登記識別情報や登記済権利証が必要になる場合でも、司法書士が上記の本人確認書類を確認し、本人に間違いがないと確認できれば登記識別情報や登記済権利証を法務局に提出せずに登記手続きが行うことが可能です。
その代わりに1.「司法書士法及び司法書士会会則に基づく」本人確認よりも厳格な本人確認が必要になってきます。
銀行融資に必要な抵当権等の担保設定登記や不動産の売買の所有権移転登記については、実務上、上記の書類がないと手続きをすることは難しいかと思います。
当事務所では原則、「本人確認情報」作成の際には、登記手続き日程にお客様と面談する予定とは別日程で事前にお客様と面談を行い、上記の本人確認に必要な書類を確認して手続きの不備を防止しております。
また、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」においても、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引、会社設立等の特定業務)について、本人確認及び記録作成等が義務付けられています場合もあります。
お客様から登記手続きをご依頼頂いた際、司法書士が本人確認の書類を提示して下さいとお願いした際は、様々な規定に基づいてお客様にお願いしておりますのでご協力をお願いします。このことによりご本人様であることを確認し、勝手に別人が手続きを行う「成りすまし」を防ぐように努めております。
以上で今回のテーマである司法書士の本人確認制度についてのお話を終わりたいと思います。
登記申請に関して何かご不明な点がありましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。
こんにちは測量部の吉村です。
我々の業務には、土地の境界確定の依頼があります。民間と民間、いわゆるお隣さんとの境界を確認し、道路(市道や府道・国道・・・水路等)と敷地との境界を確認していく作業です。
皆様は自分の敷地に接する道路の境界のことを知っていますか?
よく道路と敷地の境界は決まっているものじゃないのですか?と聞かれる事があります。
すべてが決まっている訳ではありません。京都市では公的に京都市が管理する区域を証明する図面がなかったり、現地で復元することが不可能であることがあるためです。
道路に関する図面では道路区域明示図や道路区域決定図などがあり、境界明示図など似たような名称の図面があり、各市町村によって呼び名はさまざまですので馴れてない方は混乱するかも知れません。
道路区域明示図とは、道路管理者が管理する道路の範囲を示した図面です。この図面は土地の境界と道路の区域が一致しないことがあるために土地の地積更正登記などを行う際の土地の境界の証明書として使用はできません。土地の境界に関する証明書は境界明示図または奥書証明書といったものがあります。
道路区域決定図も私道を市道として認定した場合に作成される図面であるため土地の境界に関する証明書として登記申請等に必要な書類として使用できます。
例として京都市での道路の境界明示申請に関する手続の流れは
- まず、京都市役所内の道路明示課へ行き、道路の区域が決定されているかどうか調査します。道路区域が決定していれば手数料等を支払い、その場で証明書を発行してもらえます。境界明示図に関して決定しているかどうかを調査し、確定していれば土地境界証明申請書を土地所有者が申請者となって印鑑証明書を含めた添付書類を準備して申請することになります。この証明書もその場で発行してもらえます。
- 調査の結果、道路明示がされていない区域である場合には、土地所有者(代理人)から道路区域明示の申請を行います。
- 申請書に不備がなければ2週間から3週間で担当職員が決定し、申請者(代理人)へ連絡が入ります。
- 道路明示課の担当職員が1〜2週間の内に申請個所へ行き、現地調査を行います。
- 道路明示課の担当職員と申請者・代理人・隣接土地所有者等の関係者と現地にて立ち会います。隣接土地所有者等に関しては我々が現地にきていただけるように案内をし、申請土地の対側の方の立ち会いも必要となる場合があり、2〜3週間程度で日程調整を行い、立ち会いの日を決定していきます。
- 立ち会いで確認した道路の区域等を測量し、京都市(京都市の測量登録業者)が立ち会いから2〜3週間かけて道路区域明示図等を作成します。
- 道路区域明示図が完成した後はその図面の同意書を作成し、関係する土地所有者に署名・押印してしてもらいますので1〜2週間はかかります。
- 道路区域明示図の同意書の提出後、道路区域明示等の決定手続を行い、完了したら、道路区域明示図等の図面を渡していただけます。
道路区域明示の調査から道路区域明示の完了後の図面を渡してもらうまで普通最低でも3ヶ月以上はかかります。また隣接する土地所有者等の関係でさらに時間がかかることもあります。
土地の境界確定業務を行っていくには官民の調整も含め、隣接者の対応に関して、迅速に対応し、境界を確定していきます。
こんにちは
司法書士の安田です。
相続税対策という言葉を聞いたことがあると思います。生前のうちにあの手この手を使って、将来自分が亡くなった際に、相続人が支払う相続税の額を減らすことをいいます。
平成27年に税制改正があり、相続税の基礎控除が大きく下がりましたが、それでも相続税を納めるために相続税申告が必要な方は、8.1%といわれています(国税庁HPより)。
これ以外の方には、相続税対策をしたおかげで相続税申告が必要なくなったという方もいらっしゃるかと思いますが、それでも相続税対策が必要な方というのはそこまで多くはないのかもしれません。
それでは、自分は相続税の基礎控除を超えるほどの資産をもっていないから相続税対策は必要ないと思っている方は本当に相続税対策をしなくてもいいのでしょうか。
答えは、相続税対策はしなくてもいいかもしれないが、相続対策はする必要があります。
ここでいう相続対策とは、相続税だけの対策ではなく、自分が亡くなった後、スムーズに相続人に対して、資産を承継させるための対策のことを指します。相続人間で揉める「争族」対策という意味も含んでいます。
例えば、私は現在、30代半ばで妻と幼い子供が二人います。資産は家と多くない預貯金くらいしかありませんが、もし、今、私が死んでしまった場合、遺された相続人はどうなるのでしょうか。
恐らく、私が死ねば、妻は子供を連れて、実家のある地方へ戻ると思います。
そうなったときに、団体信用生命保険のおかげで今の住宅ローンはなくなるので、今の家を売って、しばらくの生活の糧にしてもらえたらと考えていますが、実際に何も対策をしていないと以下のようになります。
まず上述の通り、団体信用生命保険のおかげで住宅ローンの支払いは止まります。
続いて家を売却するために相続登記をしなければなりませんが、相続人である二人の子供は未成年であるため、妻と子供で遺産分割協議をすることができません。
この場合に、遺産分割協議をするには、未成年の子供一人一人に特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
また、特別代理人を選任した場合でも、遺産分割協議の内容は自由に定められるものではなく、法定相続分を意識した内容で、遺産分割協議をしなければなりません。
そもそもかなり時間がかかる上に、私としては、子供はまだ幼いので、すべて妻に受け取って管理してもらい、その中から、生活費や学費など必要なお金を使ってほしいのですが、遺産分割協議の時点で、子供の財産として管理しなければならないことになります。(結局、妻が管理するのだから同じではないかと思うかもしれませんが、大きなお金を使うときなど贈与税等を意識しなければならなくなります。)遺産分割協議が終わらなければ、売却手続きを進めることもできない場合もあります。
これでは、スムーズな遺産の承継が行えたとはいえません。
このケースで、私が相続対策として、妻にすべての財産を相続させる遺言書を遺しておけば、遺産分割協議は不要で、すぐに相続登記を行い、すぐに売却に向けて動き出すことができます。
このように、相続対策は、相続税がかからない・まだ若い・相続人同士の関係は良好だから・うちに限って揉めることはない、と考えている誰しもが、実はやっておいた方がいい対策なのです。
また、相続人の数や関係、ご自分に資産などによっては、ひとりひとりしなければならない対策というのは異なってきます。
自分が亡くなった時にどういう形で遺産を承継してほしいか、このまま亡くなった時にはどんなリスクがあるかを考えて、色々な相続対策を考える必要があります。
相続対策の代表的な遺言書やエンディングノート、その他、任意後見や家族信託さらには死後の延命措置を行うかどうかの意思表示なども相続対策に含まれます。
当事務所では、相談者様ひとりひとりの実情をお伺いした上で、最適な生前対策をご提案できるよう日々、勉強をしております。少しでもご自身が亡くなった後のことを考えることがあれば、ぜひ一度当事務所で一緒に相続対策を考えてみませんか。
こんにちは。ひかり司法書士法人の岡島です。
昨年から民法改正が親族、相続法で随時適用されています。今回はその中で、遺留分に関する改正についてお話したいと思います。
まずはじめに、遺留分とは何かということですが、簡単にいうと法定相続人が財産を取得できる最低限度の割合のことです。
例えば、父親、母親、息子2人の4人家族の場合、仮に父親が亡くなったとすると、配偶者である母親の遺留分は法定相続分1/2×1/2で1/4になります。
息子それぞれの遺留分は法定相続分1/4×1/2で1/8となります。遺産が4000万円だとすると、母親は最低でも1000万円、息子は500万円、遺産の中からもらう権利があるのです。
ちなみに、この遺留分は被相続人、上記例の父親の兄弟姉妹にはありません。
ですので、仮にこの例の夫婦に息子がいなかった場合の法定相続人は配偶者である母親と被相続人である父親の兄弟姉妹ですが、生前に被相続人が配偶者に財産を相続させるという旨の内容の遺言を残していた場合、兄弟姉妹には遺留分がないので、配偶者に対して持ち分の権利を主張することはできません。
では、改正点に関してお話していきます。改正によって何が変わるのでしょうか。
1 遺留分の金銭債権化
遺留分を侵害された場合の権利内容が変わります。
今の民法では「遺留分減殺請求権」という権利です。この権利は被相続人が第三者に贈与などをした場合で、相続人がその贈与を受けた者から、自分がもらえる最低限度の部分を取り戻すための権利です。
原則、現物返還の効力が生じ、遺留分を侵害している限度で贈与の効力を取り消すというものでした。
ですので、権利を行使しても贈与された不動産などは全てが取り戻せるわけではなく、贈与を受けた者との共有となってしまうのです。
今回の改正で、現在の遺留分減殺請求権から「遺留分侵害請求権」へと名称を変え、この侵害請求により金銭債権のみが発生するようになりました。
これにより権利を行使した場合の効果が変わり、贈与を受けた者と共有状態となってしまう問題が解消されます。なぜなら、遺留分侵害請求権は、贈与などを取り消すのではなく、相続人の遺留分の割合の分だけ金銭の請求のみができるという権利だからです。
贈与された不動産などの権利はそのままで、相続人の最低限度の権利である遺留分はお金で精算しましょうという趣旨です。
2 遺留分侵害の対象期間が相続開始の10年間に限定
今の民法では、遺留分の基礎財産(相続人の遺留分を計算するにあたって、計算の対象になる財産)に含める財産の期間に制限はなく、相続開始前にされた相続人への贈与は、何年前であろうが遺留分を侵害しうる財産の移転であり、基礎財産の計算に算入されてしまうのです。
改正後は相続人に対する贈与は、相続開始前10年間にされた贈与に限り基礎財産に算入されます。
よって仮に15年前に被相続人が相続人に贈与していた場合は、その贈与された分は計算に加えられず、取り戻されることがなくなるのです。
上記2点の改正点から、今後事業承継などがやり易くなります。
創業者である父親と息子2人というケースで、生前に父親が事業資産を全て長男に相続させるという遺言を残したとします。
この場合、後継者ではない次男には遺留分として1/4の権利があるので、遺留分減殺請求権を行使されてしまうと、長男3/4、次男1/4という共有状態となり、創業者亡きあとの経営がスムーズにいかなくなる不安がありました。
しかし、今回の改正により、遺留分減殺請求権は金銭債権を請求するのみの遺留分侵害請求権となったために、長男は次男の1/4の部分を金銭で解決し、事業資産である会社不動産や自社株を維持できるようになるのです。
また、遺留分を計算する基礎財産にかかる贈与は相続開始前の10年間に限定されたので、早期に長男に贈与しておけば、10年が経過することで、遺留分の問題が生じなくなります。
今回ご紹介した遺留分に関する改正が適用されるのは2019年の7月1日以降にお亡くなりになった方の相続に関してです。
この記事がこれからこの制度を利用される方のお役に立てて頂ければと思います。

私たちが携わっている業務では、実印を押して頂くことが多いです。
そこでよく「実印は押したくない」「印鑑証明書を渡すと悪用されそうだ」
などと、よく言われてしまいます。
そこで今回は、正しい実印の使い方や保管方法をお話したいと思います。
1、判子についてのあれこれ
日本はまだまだ判子文化です。
ですので、普段でも認めの判子を鞄に入れて持ち歩いてる方も多いのではないでしょうか。
まず、判子を押すということはどういうことでしょうか。
それは「この書類に書いてあることを確かに認めました」という意思表示の意味合いがあります。ですので、どんな些細な書類でもしっかりと読まなくてはいけません。
では、実印はどういうときに必要なのでしょうか。
車、家の購入や不動産売買それと相続や境界確認書などです。
信用が必要な書類になってくると「確かに本人が押した」ということを証明しなくてはいけません。
判子文化の日本らしいですね。
そこで必要になってくるのが「実印」と「印鑑証明書」のセットです。
実印とは、市区町村の役所に登録した、公的に認められた判子のことをいいます。
役所に判子を登録することを印鑑登録といい、登録された判子を実印と呼びます。
印鑑登録をすると、印鑑証明書を取ることができます。
この証明書があることで、「確かに本人が実印を使って押した書類」であることが認められます。
2、実印の使い方
実印が必要になってくる時は、上記でもでてきましたが、車、家の購入や不動産売買それと相続や境界確認書などです。
車、家を購入するときに、なぜ銀行が何百万何千万円という大金を貸してくれるかと思いますか?それは借りたお金を必ず利子を付けて返すということを本人が実印と印鑑証明書で意思表示しているからです。
実印と印鑑証明書のセットで信用度が跳ね上がるわけです。どれだけのお金を集められる、借りれるかはどれだけの信用があるかです。その信用の一つが「実印」と「印鑑証明書」です。
返すと言った、言わないで揉めなくするためには本人の意思表示が重要になってくるわけです。
そこで、言った言わないで、よく揉めるのが、「土地の境界」です。
ですので、境界確認書には実印と印鑑証明書のセットが、よく求められます。
境界確認書は土地の所有者が変わっても、次の所有者に引き継がれていくものですので、書類の信用度が重要になってきます。
隣接から境界確認書に署名押印を求められたときは、実印で対応されたほうが、これから土地を受け継がれていくであろう、ご自身の子孫の為でもあるのです。
繰り返しですが、判子を押すということは、
「この書類に書いてあることを確かに認めました」という意思表示の意味合いがあります。ですので、どんな些細な書類でもしっかりと読み、わからないことは聞き、納得する
までは押さないようにしましょう。
3、実印の悪用対策、保管方法
3-1、偽造しにくい判子を使う
3-2、実印を使うときだけ、登録する
3-3、実印と印鑑証明書もしくは印鑑カードは別々に保管する
実印は認印と違って、法的効力をもちますから非常に重要な判子です。 そのため、保管場所や保管方法には注意を払う必要があります。
皆さんはどのように保管していますか?
引き出しに、実印と印鑑証明書もしくは印鑑カードを一緒に保管していないでしょうか。
絶対にダメです。やめてください。
これをしたら必ず安心だいうことはないですが、リスクは減らせますので以下の事を試してはいかがでしょうか。
3-1、偽造しにくい判子を使う
実印は登録さえすれば、三文判でも実印としての効力は変わりません。
単純な印影の三文判では偽造されるリスクがあるわけです。
ですので、実印で使用する判子は機械彫りではなく、手彫りなどの偽造されにくい印鑑を使うことが非常に重要です。
3-2、実印を使うときだけ、登録する
実印と印鑑証明がセットになることで、強い効力を発することになります。
そこで実印を使用したらその都度、印鑑登録の廃止手続きをするのです。
つまり実印と印鑑証明が必要になったときに役所に行き印鑑登録をし、印鑑証明を発行したらすぐに抹消手続きをする。そしてまた必要になったときに登録する、という方法です。
その都度の手続きはめんどくさいですが、リスク軽減としては有効だと思います。
3-3、実印と印鑑証明書もしくは印鑑カードは別々に保管する
実印と印鑑証明書はセットで効力を発揮するものです。
別々に保管することによって、悪用のリスクは減ります。
実印の保管場所でおすすめは、銀行の貸金庫に保管するのが一番良いでしょう。
銀行の貸金庫は管理がしっかりしているので安心です。
実印を預かっていた家族が騙されるというケースもあるので、親族に預けるのも安心ではありませんしね。
4、まとめ
実印関係で、揉め事が多いのは、押して騙されることよりも、同居している親族関係が関わっている場合が多いとのことです。
なぜなら、引き出し等にセットで保管している方が多いので、他人が容易に外に持ち出せるからです。
ですので、実印は、押さなければ安心だというより、保管方法が一番大事ということです。
あとは使用方法さえ間違わなければ、大事な時にお金を借りられたり、境界などの揉め事を減らせたりできる、便利な道具です。
もし、実印を紛失してしまった場合、役所に行き印鑑登録の廃止・変更手続きを行いましょう。
悪用のリスクを減らせます。
こんにちは 測量部の道中です。
今回は地籍調査についてお話しします。
土地所有者様、地籍調査について、ご存知でしょうか?
地籍調査とは、国土調査法に基づき、主に市町村が事業主体となって行います。
地籍とは、「土地に関する戸籍」のことであり、それらを調査することです。
そして一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界を確認し、面積を測量して現地と合致する正確な地図・地積測量図及び登記簿を作成していきます。
なぜ、地籍調査が必要かといえば、現在、登記所に備え付けられている公図は、明治時代の地租改正事業によって作成されたもので、旧土地台帳付属地図であるため、精度は非常に低く、長い年月の経過により旧土地台帳と現地の形状が一致せず、土地の境界や地積が不正確なものがあるため、土地の売買や不動産取引の際、境界紛争等が生じる可能性があります。
そのため、地籍調査を行い、土地の一筆ごとに境界を確認し、精密な測量を行い、精度の高い地図・地積測量図及び登記簿を作成する必要があります。
土地に関するトラブルの話は当事務所でもよく耳にします。
例えば
- 隣が家を建てているが、自分の敷地に越境しているので確認してほしい。
- 家を建てるために隣地との境界に塀を建てようとしたが、境界がわからない。
- 土地を売ろうとしたが正確な面積がわからなかった。
- 土地を購入したが、登記簿の面積と実際に測った面積が違った。
などですが地籍調査を行うことによって精密な地図が作成されることで、土地の位置が特定できるので、上記のような境界に関するトラブルを未然に防ぐことができます。
又、法務局に備え付けられた地積測量図は座標を持つため、境界標が亡失しても座標に基づいて復元が可能であり、災害復旧の迅速化にもつながります。
主に市町村が主体となる地籍調査事業の作業手順としては以下の手順で行われます。
- 事業計画・準備
- 一筆地調査
- 基準点測量
- 立会い
- 立会い後一筆地測量
- 世界測地系による地積測量
- 閲覧・訂正
- 承認・認証
- 行政主体への備え付け・法務局への送付
これらの作業手順を経て、土地が現地と合致した地図や登記簿になり、法務局において登記され公示されます。
今回は行政が主体となって行う地籍調査についての話になりましたが土地や建物の測量に関する疑問点や気になることがある方はお気軽にお問い合わせください。
今回は、突然、家を失ってしまうかもしれないという怖い話をしたいと思います。
あなたの家が建っている土地は誰の名義になっているでしょうか。
自分の名義だよっていう声が沢山聞こえてきそうですが、実は、全ての人がそうとは限らないのです。
建物は自分名義だけど土地は他人名義になっているという人は意外と多いです。
それは、土地を借りて、家を建てている言わば、土地を借りているという状態なのです。
そうか!地主に突然出て行けと言われて、出ていかないといけないくなるのかと思ったあなた、簡単に言えばその通りですが、ちょっと違います。
なぜなら借地人は、借地借家法で守られていて、正当な理由が無いかぎり、出ていく必要はないので、いくら地主でも急に強制的に出て行かすことはできないのです。
借地借家法とは
土地の貸し借りや、住宅の貸し借りには借地借家法という法律が適用されます。
「借地(土地を借りる)」と「借家(家を借りる)」のために規定された法律で、借りる側に強い権利を与え、借主を保護する法律となっています。
「土地を貸したら帰ってこない」という覚悟で土地を貸し出さなければならないと、よく言われているぐらい、借主よりの法律となっています。まぁ住むことは憲法で守られているので当たり前ですが。
時代が変わって地価が上がってくると、地主側からすると、安い地代で貸しているよりは、ビルでも建てたほうが良いとなり、借地人に対して土地を返してとなるわけです。
しかし、簡単には借地人は返してくれません。なぜなら、親の代から借りているなど昔から借りている場合は、当時の価値での地代で借りているので、今の周辺相場からするととんでもなく安く借りられているのです。
ここからが怖い話になります。
不動産にはいろいろな悪い人が関わってきます。最近で言えば地面師ですね。
バブル時代には地上げ屋というのが暗躍しておりました。
地上げ屋とは、建築用地を確保するため、強引な手法による不動産の売買を進めていく人のことです。
その一つが借地人を強制的に出て行かすというものです。地価が上がりそうな土地を買って、借地人を出て行かし、土地を高値で売るというものです。
ではどうやってするのかというと、
まず借地上の建物を壊します。そして建物滅失の申出をします。後は土地を売るなり、ビルを建てるなりするわけです。
借地借家法では、建物を利用することを目的として土地を借りる場合を想定しています。
ですので、借地上の建物が無くなると借地借家法の効力がなくなるわけです。
どうやって建物を壊すかは、ここでは言えませんが、悪いことをする人はよく考えるものです。
壊した後は、通常は建物所有者からする建物滅失登記を、所有者不明として、土地所有者から申出をして、借地借家法の適用となる借地上の建物を滅失するわけです。
これはバブルの話だけでなく、オリンピックや万博で地価が高騰しているので、今でもあることなのです。
ネットで検索すると、借地関係の地上げ事例が出てきます。
住んでいる居宅だけでなく、遠くにある倉庫とかでもあります。遠くにある倉庫は頻繁に行くことはないので、行ってみると無くなっているということもあるのです。
対策としては、家を長期間空き家にしないということと、一番は、地主と良好な関係を続けること、周辺相場より安い地代に関しては、地主と協議し、相場に近づくように努力するなどが挙げられます。
話がそれますが、建物を壊されたら、裁判をしたら良いのでは?というのがありますが建物の賠償請求はできたとしても、土地は返ってこないので、どこかに引っ越さなければいけないのです。住み慣れたところを離れるのは辛いですよね。
法律で守られていると言っても、その権力に溺れないように気を付けなければいけないということです。
人間は一定の権力を持つと、自分を客観的にみることができなくなり、正しい判断ができにくいというのがあります。
自分は守られているから、何をしても良いんだ、自分が正しいのだと思い始めたら要注意です。
まぁそうなってはバイアスが掛かってしまってますので、すでに遅しとなりますが、この記事を読んでいるあなたはまだ大丈夫です。権力に溺れず借地人としての正しい判断をして、地主と良い関係を続けてください。
以上簡単ではありますが、「突然、家を失ってしまうかもしれないという怖い話」をお話しました。
固定資産税評価証明書とは
不動産の「固定資産評価額」を証した書類であり、その年の4月1日から翌年3月31日までの1年間の不動産の固定資産税上の不動産評価額を示すものです。
この評価額は毎年4月1日の新年度から適用され、新しい評価額に基づき固定資産税や都市計画税が計算され、課税通知書又は納税通知書として、不動産の所在地の各市町村から所有者へ郵送されます。
新年度の固定資産評価額を知るには?
固定資産評価額をお知りになりたい場合は以下の2つの方法があります。
- 「納税通知書」に同封された「課税明細書」で確認する
毎年5月~6月頃に市税事務所や市町村から送られてくる固定資産税の納税通知書に同封されている「課税明細書」の記載を見れば、最新の評価額を知るそとができます。課税明細書には記載されている数字が多いですが、見るべきポイントは「価格」あるいは「評価額」という文字です。これらに記載されている数字が、所有されている不動産の固定資産評価額になります。
- 固定資産評価証明書の請求を行う
不動産を管轄する市税事務所や市町村役場では、固定資産評価額だけを証明した「固定資産評価証明書」の手数料(一通300円程度)を支払うことで取得することができます。
単に新年度の評価額が知りたい場合は①の方法で十分でしょう。
手数料を払う必要もありませんし、郵送でお手元(納税義務者の)に届くので、楽に確認することができます。
しかし、郵送で送られるのが5月~6月になる市町村が多いので、早く評価額を知る必要がある場合や登記申請を控えている場合は②の方法を行うことになるでしょう。
登記申請に評価証明書を使う場合の注意点
登記を申請する場合、法務局に納める「登録免許税」を計算するために評価証明書を添付する必要があるのですが、申請する時期で何年度の評価証明書を取得すべきなのかが変わります。
切り替えの基準となるのは「毎年4月1日」です。
ですので、これから登記申請で添付すべき評価証明書の年度は平成31年度となります。
平成30年度のものを取得してしまった、あるいはもともと持たれていたとしても登記申請には使えません。
再度評価証明書を取得する必要があります。また不動産の評価額が変わってしまっている場合は、登録免許税の計算をやり直す必要もあります。※(相続登記の際の税率は、1000分の4 評価額が1000万円の場合 登録免許税は4万円)
これから登記申請、特に相続登記をご自身で行う場合はご注意ください。
戸籍や住民票と違い、固定資産評価証明書は登記申請において最新年度のものが要求されます。
市町村等の窓口で請求される場合は使用目的を窓口の方にお伝えしてから、交付申請書類をご記入されるのが良いかと思います。そうすれば市町村の係りの方が必要な評価証明書の請求方法を教えてくれるはずです。
以上で今回のテーマである固定資産評価証明書についてのお話を終わりたいと思います。
登記申請に関して何かご不明な点がありましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。

先日、新しい元号が発表されましたね。
「令和」
日本古典である万葉集から初めての採用ということで話題になりました。
また、「令」の漢字が日本の元号に使用されるのも初のようです。
今回は、そんな元号と登記のお話です。
不動産の登記記録には登記の年月日や登記原因日付など、「年」を登記事項として記載することが多いのですが、登記記録は年を「西暦」で記載することはできず、全て「元号」にて記載されます。
元号にて記載しなければならない根拠ですが、これは法律(不動産登記法)に書いてあるわけではなくて行政通達による実務上の運用となっています。
実際に不動産登記法では下記のように「年月日」とだけしか規定されておりません。
「不動産登記法第59条 」
権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一 登記の目的
二 申請の受付の年月日及び受付番号
三 登記原因及びその日付
そもそも元号は皇室典範にて規定があったのですが、戦後の日本国憲法制定にあたって皇室典範が改定されたことにより、元号の法的根拠が失われていた時期が続いていました。
しかし官民問わず、昭和という元号がそのまま一般的に使用され続けてきたのです。
そして昭和54年に「元号法」が施行され、元号の法的根拠が復活することになりました。
「元号法」
- 元号は、政令で定める。
- 元号は、皇位の継承があった場合に限り改める。
元号法は、たった2項だけの構成という、極めて短い法律としても有名です。
その元号法が施行された際に、登記及び供託事務の取扱いについての依命通知が出されました。
「昭和54年7月5日民三第3884号・民事局第四課長依命通知」(一部抜粋)
申請書及びその添付書面中の日付の記載として西暦を用いても、登記記録に日付を記入するときは、すべて元号を用いることとする。
そのため登記申請書を西暦で作成したとしても、登記記録には元号にて記載されることになります。
例えば申請書に2019年5月15日売買と記載した場合であっても、登記記録には令和1年5月15日と記載されます。
また、「元年」も登記記録には記載されず、「令和元年」は「令和1年」と登記記録に記載されるようです。こちらは通達とかではなく法務局のシステム上の都合だとか聞いたことがありますが、本当にそれだけの理由なのでしょうかね。
最近では西暦にて契約書等を作成する金融機関も増えてきましたが、どちらかに統一されていないと申請書作成の際に間違えてしまいそうで司法書士としては注意が必要です。
余談になりますが、新元号の「令和」から「西暦」に変換したい場合は、令和に「018(レイワ)」を足して計算すると分かりやすいそうですね。
例)
令和1年+018=西暦2019年
令和5年+018=西暦2023年
以上、元号と登記のお話しでした。

平成30年度も終わり、新元号も発表され、平成最後の年度となりました。
日本では、1月から12月までの1年間と4月から3月までの年度という考え方があります。
不動産に関することでいえば、4月1日から新しい年度の評価証明書を取得することができ、4月以降の不動産の登記の申請に関しては、31年度の固定資産税評価額が課税価格となります。
そして、早いところでは、4月の上旬には、固定資産税の納税通知書が届きます。よって不動産をお持ちの方のところにはこれから、続々と納税通知書が届くことになります。
今回は、この固定資産税の納税通知書についてお話をしたいと思います。
ちなみに固定資産税とは地方税であり、各不動産の所在の市町村が課税主体となります。ただし、東京23区については、区ではなく都が課税しています。。
各市町村及び都によって、納税通知書が送られてくる時期や記載されている情報には違いがあり、すべての市町村にあてはまるわけではありませんが、ある程度、読み取れる内容は決まってきます。
ちなみに固定資産税の納税通知書といいますが、ほとんどの場合、固定資産税と都市計画税の合算した金額を支払っています。単純な計算方法でいくと固定資産税は、評価額の1.4%、都市計画税は評価額の0.3%ですが、実際には評価額から課税標準額を計算して、その課税標準額に税率を掛けることになります。細かい計算については私も詳しくはわかりませんので、割愛致します。
読み取れる内容① 不動産の名義人がわかる。
納税通知書は、基本的には不動産の名義人宛てに届きます。よって、亡くなっている方名義で届く場合、名義変更が出来ていない可能性があります。
その場合は、速やかに相続登記をすることをお勧め致しますので、その際はひかり司法書士法人にご相談ください。なお、確実に現在の不動産の名義を調べるには、最寄りの法務局へいって、登記事項証明書を取得しましょう。登記事項証明書は、法務局へ行けばだれでも全国の物件の所有者を調べることができます。
読み取れる内容② 不動産固定資産税評価額がわかる。
固定資産税納税通知書と同封して、課税明細書が送られてきます。この課税明細書は、評価額や課税標準額などが記載されております。たとえば、不動産の名義変更や相続税の申告など評価額がわからない場合は、役所で評価証明書を取得する必要がありますが、この課税明細書があれば、評価証明書を取得しないで済む場合がほとんどです。また、評価額がわかれば、名義変更の際に必要な登録免許税の計算ができますので、登記手続きの見積書を作成することができます。
読み取れる内容③ 新築建物の軽減額がわかる。
新築建物の場合、3年間(マンションの場合は5年間)は固定資産税が半分となります。さきほどの課税明細書には、軽減されている額などが記載されている場合もありますので、そこから、軽減が終了した後の固定資産税を計算することができます。
読み取れる内容④ 市場価格が大体わかる。
こちらは参考程度ですが、固定資産評価額は公示価格の7割程度といわれており、公示価格とは、土地の取引価格に対しての指標、公共事業用土地取得の価格算定の基準となっています。よって、売却したいと思った時に、評価額から割り戻しをすればどの程度で売れるのか参考になります。ただし、不動産はちょっとしたことで値段が変わりますので、あくまで参考程度にしてください。
いかがでしょうか。
固定資産税の納税通知書がきても納付だけして、あとはどこに行ったからわからないという方も多いのではないでしょうか。
今年度に届いた固定資産税の書類はせめて次年度の分が届くまで、お手元にもっておけば、急に評価額が知りたいとなった時に役所へいかなくてもわかりますので、お手元に保管されることをお勧め致します。
毎年この時期になると、確定申告をしなければ。。。
という言葉を耳にします。
確定申告とは、所得にかかる税金の額を計算し納税するための手続きです。
個人の方の場合、1月1日から12月31日の1年間の所得を、翌年のこの時期(2019年は2月18日から3月15日まで)に税務署に申告する必要があります。
会社員の場合は年末調整を行っているので、通常は確定申告を行う必要はございません。
年末調整は毎月給与から概算の所得税を天引きし、年末に正しい所得税を算出して、足りない場合は追加で納付、支払いすぎている場合には還付される仕組みです。
還付の場合は臨時収入みたいでうれしい気分になるのですが、実は源泉徴収されている自分のお金が戻ってきただけなんですけどね。
通常であれば会社員の方は確定申告をしなくてもよいのですが、会社員でも確定申告が必要になる主なケースとしては次のようなものがあります。
会社員でも確定申告が必要になるケース
- 給与収入が2,000万円を超えている
- 医療費控除を受ける場合
- ふるさと納税の納付先が6か所以上
- 不動産所得が20万円を超える場合
- 住宅ローン控除を初めて受ける場合
司法書士の仕事を行っていて、この中で良く聞くのが不動産所得の申告です。
日頃から不動産の売買に関わる仕事をしておりますので、お客様からも相談される機会があります。
不動産を売った場合に生じた所得に対しては、譲渡所得税という税金が課税されます。
簡単にいうと不動産を売却した金額から、購入した金額と経費を引いて差額があればその差額が譲渡所得として課税されるのです。
譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
マイホームの売却であれば譲渡所得から3,000万円が控除されますので、譲渡所得税を納めるケースは少ないのですが、問題になるのがご自身が住んでいない不動産を売却するようなケースです。
代表的なものとして、相続した実家を売却する場合ですね。
この場合は、3,000万円のマイホーム控除を使うことができませんし、親が購入した当時の金額が分からなければ取得費が5%となってしまい、譲渡所得税も高額になってしまいます。
しかしそのような方にお得な制度もございまして、それが被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例というものです。
要件は色々とあるのですが、この特例を使うことが出来ればマイホーム控除と同様に、譲渡所得が最大3,000万円が控除されますので、収める税金が600万円近くも減額されることもあります。
以下に空家控除の要件を簡単に記載しますが、詳しくはお近くの税務署にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の要件
- 相続の開始直前に被相続人のみが居住をしていた家屋
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物(区分所有を除く)であること
- その家屋を相続又は遺贈により取得
- 相続の時から売却の時まで賃貸等、他の用途に使っていない
- 当該家屋を取り壊して更地にして売却(または耐震リフォームを行い売却)
- 相続の開始日から3年を経過する日の年の12月31日までに売却
- その売却代金が1億円以下であること
沢山の要件がありますね。
制度の概要としては、近隣に迷惑をかける恐れのある古い家屋を相続した場合、早めに建物を解体してから売却すれば税金をまけてあげますよ。といった感じでしょうか。
この特例があることにより、放置された空家問題の解消につながるのでしょうね。
また先日発表された、平成31年度税制改正大綱では、上記要件のうち被相続人の居住について変更になるようです。
現行の制度では、相続開始直前まで被相続人の居住の用に供されていることが要件でした。
このため、被相続人が老人ホームへ入所したまま亡くなった場合には、たとえ被相続人の自宅が空き家になっていてもこの特例を受けることができませんでした。
しかし、改正案では被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも、以下の追加要件等を満たす場合に限り、この特例を適用できるようになります。
①被相続人
- 介護保険法に規定する要介護認定等を受けていること
- 相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと
②被相続人の居住家屋について、被相続人が老人ホーム等に入所したときから相続開始の直前まで
- 被相続人による一定の使用がなされていること
- 事業、貸付の用、被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと
また、上記の改正は2019年4月1日から2023年12月31日までに行う譲渡についての適用となります。
関連記事
皆様は土地や建物の不動産登記の変更や更正を行うときに司法書士と土地家屋調査士と言う資格(職業)があることをご存知でしょうか?
今回はこの二つの職業の違いをご紹介させて頂きます。
業務での違い
司法書士と土地家屋調査士はどちらも主に不動産登記を扱う職業になります。
司法書士は不動産の権利に関する登記申請を取り扱うのに対し、土地家屋調査士は不動産の物理的な状況を正確に把握するために調査や測量を行い登記申請を取り扱う職業になります。
司法書士とは
司法書士の主な業務は、登記・供託などの手続き代理です。
土地やマンション、家屋など不動産の権利関係を登記として記録するための書類作成、および申請代理を行います。
また、供託とは法律行為の達成を目的に公的機関に財産などを預ける制度で、その申請代理を司法書士が行います。
これらは司法書士法で定められた司法書士の独占業務になります。
また、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における訴訟事務を行うことが認められています。
訴訟手続きのほか、支払督促手続きや民事調停手続きなど、簡易裁判所管轄の事案についての代理が行えます。
土地家屋調査士とは
土地家屋調査士の主な業務は、不動産の物理的状況(土地の大きさや建物の形状等)を正確に登記記録に反映させるのに必要な調査や測量を行います。
土地又は建物の物理的な状況を把握するためには過去の資料調査や、現地での測量を行います。
また、筆界特定の手続について代理申請等も行います。
筆界特定の手続とは、隣接する土地の所有者間で境界に争いが生じ民間で解決できないケース、又は隣接土地所有者の行方がわからず、境界協議ができない場合等に法務局の筆界特定登記官が土地所有者等の申請により境界線を特定する制度であり、専門的知識を有する筆界調査委員の調査結果と意見を踏まえ申請人、関係人の弁明、提出された資料等により総合的に判断し特定する制度です。
これらは土地家屋調査士法で定められた独占業務になります。
簡単ではございますが2つの資格(職業)にはこのような違いがあります。
一般の方で、司法書士と土地家屋調査士の業務の違いがわかる方というのそこまでいないと思います。
この案件は司法書士に頼めばいいのか、土地家屋調査士に頼めばいいのかわからないということは、大いにありえます。
弊社では、ひかり司法書士法人とひかり測量設計さらに土地家屋調査士と提携をしておりますので、不動産登記に関するお悩みであれば、ほとんどの問題に対応することができます。
土地の境界のことや建物の名義変更のことなどに関して、やらなければいけないけれど放っておいてるようなことはありませんか。
不動産の名義変更をすると税金がかかる?
不動産の名義変更とは、売買、贈与、相続など何らかの事由で不動産の所有権を移転させることをいいます。
所有権を移転させるということは、新たな所有者は移転された不動産の分だけ財産が増えたことになります。
つまり、不動産を譲り受けた方が得をした場合には、その得した部分に税金が課税されます。
課税される税金とは?
1、登録免許税
登録免許税とは、新たに不動産の所有者となった方の名義を登録する際にかかる税金であり、不動産の名義を変更した際には必ずかかってくるものです。
| 売買→ | 不動産価額の15/1000(土地)、20/1000(建物) |
|---|---|
| 相続→ | 不動産価額の4/1000 |
| 贈与→ | 不動産価額の20/1000 |
以上の割合で登録免許税がかかってきます。
仮に1000万円の土地の場合ですと、売買→15万円・相続→4万円・贈与→20万円となります。
2、不動産取得税
不動産取得税は、不動産の移転の事実に着目して課税されます。
そのため、不動産を取得した方は基本的に不動産取得税の支払いが必要です。例えば、土地を購入した場合の不動産取得税は、原則として取得した不動産の固定資産税評価額に3/100の税率をかけた金額となります。
3、相続税
父親がなくなり、遺産の中に不動産があった場合には、その父親が所有していた不動産の名義変更をする必要があります。
この際に父親の全ての財産総額が相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えている場合には、相続税の申告の必要があります。
仮に父親の財産総額が基礎控除額を下回っていれば、相続税を支払う必要はなく、相続税の申告も不要です。
ただし、不動産を相続することによって名義変更をする場合には、登録免許税の支払いが必要です。なお、相続により不動産を取得した場合には不動産取得税は課税されません。
4、贈与税
生前に父親から子供に不動産の名義を変更するといった場合で、子供が不動産の所有者である父親に全く対価を支払わない場合には、子供はタダで不動産を取得したことになります。
その場合には、父親から子供へ不動産を贈与したことになるため、受贈者である子供は不動産の価格に見合った贈与税の税率に相当する贈与税を支払う必要があります。なお、贈与税算定の際の不動産の評価は基本的には土地については路線価を使用し、建物については固定資産税評価額で評価します。
5、所得税
相続不動産を売却する際に対象となる不動産が購入時より値上がりしていた場合には、譲渡所得が生じます。対象不動産の売却先としては、親族であっても申告が必要です。
確定申告の時期は?
1、相続税の申告期限
「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に行うことになっています。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などにあたるときは、これらの日の翌日が期限となります。
2、期限を過ぎてしまったら
相続人が遠方にいる場合などで、申告書の作成や押印が間に合わなかったため期限内に申告できなかったときは、相続税とは別に無申告課税や延滞税がかかってしまうので注意が必要です。
また、相続税がかかることを知りながら故意に申告書を提出しない場合や、財産を隠蔽するような悪質なケースでは、重加算税という更に重いペナルティが課されます。
3、相続税の申告書の提出先
相続税の申告は、相続や遺贈によって財産を取得した人が行いますが、相続人が複数いる場合でも、人数分の申告書を作成してそれぞれが提出する必要はありません。1通の申告書に全員が署名・捺印して、それを被相続人が死亡した時の住所地を管轄する税務署に提出します。この時の注意点は、相続人の住所地を管轄とする税務署ではないことです。
4、贈与税・所得税の申告期限
贈与税と取得税については、1月1日から12月31日までの1年分に行われた贈与や売買により発生した所得については、翌年の2月から3月の確定申告の時期に申告をする必要があります。
昨年2018年にあった贈与や売買によって得た所得に関する申告であればそれぞれ以下の通りとなっています。
| 贈与税 | 2019年2月1日(金)~3月15日(金) |
|---|---|
| 所得税 | 2019年2月18日(月)~3月15日(金) |
5、贈与税・所得税の申告書の提出先
これらは、相続税の申告と異なり、贈与であれば、贈与を受けた者の住所地を管轄する税務署となり、所得税は所得を得た者の住所地を管轄する税務署となります。
不動産の名義変更はいつまでにしなければならないという期限はありません。しかし、それに伴う税金関係の申告手続きがある場合には申告の期限がございますので、まずはご自身の場合は名義を変えることによって税金の課税があるのかないのか、それを把握されることが重要だと思います。この記事がお客様の名義変更、確定申告の参考になれば幸いです。
こんにちは。ひかり司法書士法人の岡島です。
今回は相続法改正関連の中で配偶者居住権についてお話したいと思います。
「配偶者居住権」とは
配偶者居住権とは被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していた場合、その居住建物の全部について無償で使用及び収益する権利です。(民法1028条本文)今までは建物の所有権と居住権を一体として扱ってきましたが、この改正によりその2つを別個の権利と捉え、「居住権」という新たな権利が創設されました。
ただし、この権利はその名の通り、配偶者にだけ認められた権利であり、被相続人が相続の開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合(ex.夫と息子の共有)には、配偶者居住権が発生しません。(民法1028条ただし書き)
二種類の居住権
この配偶者居住権には「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の二種類があります。
「配偶者短期居住権」は、配偶者が相続財産である建物に相続開始のとき無償で居住していた場合は、遺産分割によりその居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日の何れか遅い日まで、居住建物を無償で使用することができる権利をいいます。
「配偶者居住権(長期居住権)」は、配偶者が相続財産である建物に相続開始のとき居住していた場合で、以下の(ア)~(ウ)の何れかに該当するとき、その居住建物を無償で使用及び収益する権利をいいます。
- 遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき(1028条1項1号)
- 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき(民法1028条1項2号)
- 遺産分割の審判を得たとき(民法1029条)
短期居住権は譲渡することができず、他の全ての相続人の承諾を得ない限り第三者に使用させることができません。
また使用貸借類似の法定債権で、資産性がないため、相続財産として考慮する必要はありません。
これに対して長期居住権は遺産分割において考慮されますので、配偶者の他の財産の取り分が配偶者居住権相当額だけ減ることになります。
売却したり第三者に自由に賃貸することはできませんが、利用権として相応の経済価値があるため、相続財産として計算する必要があります。長期居住権の存続期間は当事者間で決定することができますが、定めがない場合は終身の間(配偶者が死亡するまで)とされています。(民法1030条)
新たな登記することができる権利
居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います。(民法1031条第1項)
通常の賃貸借は、賃貸人に登記義務はありませんでしたが、配偶者居住権(長期)は、所有者に登記義務を負わせています。この配偶者居住権の設定登記がなければ、第三者(居住建物を購入した人など)に、配偶者居住権を主張することができません。(民法1031条第2項)
被相続人が生前に設定していた担保権には、登記の前後で劣後するため対抗できないものと思われます。
今回は配偶者居住権についてお話ししましたが、それ以外にも重要な改正部分、また債権法の改正に関しても重要なものを選んで情報を発信していきたいと思います。
明けましておめでとうございます。
ひかり司法書士法人の冨永です。
毎年お正月明けには、相続登記の問い合わせが多くなっております。
おそらく年末年始に帰省された際に親戚一同が集まったタイミングで、実家の名義変更をまだ行っていないといったお話しをされるのでしょうね。
今回は遺言書に関する法律改正のホットな話題。今年の1月13日からの改正内容です。
遺言書のなかで一番簡単に作成することが出来るものが「自筆証書遺言」です。
紙とペンと判子さえあれば、どなたでも作成することができるのですが、自筆証書遺言は、遺言書の内容の「全文」を「自筆」で書く必要があります。
不動産の表示や預金、株式などの財産目録も全てを自筆にて記載する必要があるのですが、これがなかなか大変なのです。
不動産がご自宅だけの方の場合はまだ良いとして、いくつも不動産や預貯金をお持ちの方になると、全てを自書するのは本当に大変な作業になります。
しかも記載を間違えていた場合、その遺言書が使えなくなる可能性も出てきてしまいます。
遺言書を書かれた方がお亡くなりになられた後では、遺言書の内容を訂正することが出来ませんからね。
今回の改正では、自筆証書遺言の「財産目録の部分」をパソコンで作成しても良くなりました。
自筆証書遺言にパソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を目録として添付したりもできます。
今回の改正は高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するための改正とされています
要するに相続をめぐる紛争が年々増えているのでしょうね。
せっかく作成した遺言書が、記載内容の不備により無効になったり、逆に争いの火種となることもあります。
遺言書の作成は、是非とも専門家にご相談ください。
こんにちは。ひかり測量設計の道中です。
今回は、復元測量についてお話しします。
測量は土地の高低差の状態や位置・面積などを測ることにより現況測量・境界確定測量・復元測量などがあります。
復元測量とは境界標が不明な場合に過去に測量された既存資料から筆界点を復元し、現地に境界標を設置する測量です。
境界標が無くなる理由としては
- 解体工事で建物やブロック塀などと一緒に撤去されてしまった。
- ブロック塀の増設工事でブロック塀の下に埋もれてしまった。
- 道路上にある境界標が車などに踏まれて亡失してしまった。
- 宅地造成などで盛土を行った為、地盤が上げられ境界標が埋もれてしまった。
- 境界標がプラスチック杭であったため経年劣化で腐食してしまった。
- 故意に隣接者や関係者が抜いてしまった。
など多岐に渡ります。
業務の流れとしては
- 資料調査
- 現地調査
- 境界立会い
- 境界標埋設作業
- 隣接者などへの確認
になります。
資料調査では法務局の公図、地積測量図、登記事項証明書や必要があれば役所で土地台帳等を調査します。現地調査では実際に現地に赴き、境界標があるかないか資料を参考に調査し、隣接の方にお話を聞き境界に関して聞き取り調査を行います。境界立会いで境界を確認したら境界標を埋設し、隣接の方へ確認して作業終了になります。
土地を所有されている方で境界に関して気になることがございましたら、ひかり測量が迅速に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。