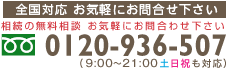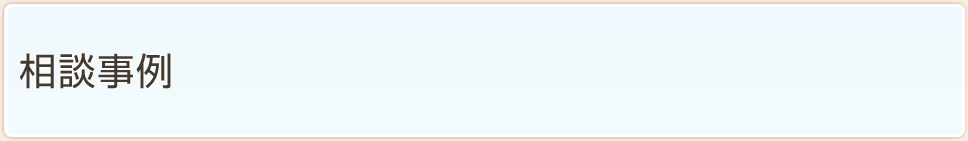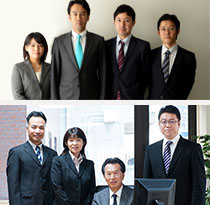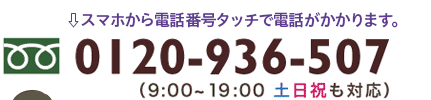こんにちは、司法書士の安田です。
私は京都市内のマンションに住んでいるのですが、先日平成29年度のマンションの固定資産税の納税通知書が届きました。以前はゴールデンウィーク明けくらいに届いていたようですが、今年は四月の前半に届きました。
年々通知が届くのが早くなっているような気がします。それだけ早く税金を支払ってほしいということでしょうか。
また、今年は新築から5年が経過し、新築建物の固定資産税の軽減が無くなる年だったので、納付額があがっているかなとドキドキしながら見たところ、なんと、去年度の1.5倍以上になっていました。想像以上に上がっていたのでしばらく放心状態でした。こればかりはどうしようもないのでがんばって支払っていきます。
ちなみに「固定資産税の軽減とは」
新築建物の場合、3年間(一定要件を満たしたマンションなら5年間)建物分の固定資産税を半分にするという軽減です。土地分及び都市計画税はそのままです。
固定資産税の納税通知書は登記名義人宛に届きます。
よって登記名義が亡くなった方の名義のままで相続登記がされていない場合は亡くなった方名義で届きます。役所は税金さえ払ってくれれば誰の宛名でも構わないというスタンスですので、一度納税通知書の宛名を見て亡くなった方名義で届いていれば相続登記が必要です。
そんな時はひかり相続手続きサポーターまでお気軽にお問い合わせください。
全国どこでも対応出来ますし、戸籍収集などできる限りご自分では何もせずに相続登記手続きを完了させることが出来ます。
この機会に一度不動産の名義をご確認をされてみてはいかがでしょうか。
関連記事:
昨年に亡くなった、父名義の家の固定資産税納税通知書が届きました。どうしたらいいですか?
みなさん、こんにちは。
ひかり土地家屋調査士法人の大栢です。
「現況測量」と「境界確定測量」の違いについてお話したいと思います。
測量の目的は、地上の状況を把握し地形図を作成することが目的です。
地形図を作成するための地形測量は、地上の地物や地貌(ちぼう)、すなわち土地の起伏その他の地形の特徴などをできるだけ忠実に表現するための測量です。
国土地理院発行の5万分の1や2万5000分の1の地形図はその代表例ですが、5万分の1図のほうは明治・大正時代に平板測量でつくられ、2万5000分の1図のほうは大半が写真測量によりつくられています。
現況測量とは、地形図作成のような広範囲の測量ではなく、あくまでも必要な場所について、現在の土地の状況をそのまま反映させただけの測量であり、ブロック塀・建物・既存境界標等の現地に存在する地物を測り、対象土地のおおよその寸法・面積・高さを知りたいときにする測量です。
土地境界については調査や確認を行わないため、算出される土地の面積は「現況面積」と呼ばれ、境界確認後の「確定実測面積」とは寸法や面積が異なってくることが多く、注意が必要です。
また、土地境界に関しては、道路管理者や隣接土地所有者との立会を行いませんので、費用を安く抑えられ、作業も比較的短期間で終了致します。
境界確定測量とは隣地所有者の立会い及び確認や官公署の図面をもとに土地の境界を全て確定させる測量のことです。
土地分筆登記や土地地積更正登記を行う場合は、申請を行う土地について、境界確定測量により境界が確定していることが必要です。
境界確定測量を行う場合は、以下のような手順を踏みます。
- 法務局調査・・・・法務局にて、依頼地や隣接土地について、公図・地積測量図・全部事項証明書等の必要な資料の収集作業を行います。
- 現況測量・・・・・上記で説明したとおり、土地の状況について測量し、現況測量図を作成します。
- 道路境界確定・・・道路と依頼地について、境界が確定しているかどうかの調査を行います。確定が出来ていなければ、道路との境界確定を官公署と行います。
- 隣接地立会・・・・隣接土地所有者と境界について、法務局資料や現況測量図を用いながら、現地立会の上境界を確認します。
- 筆界確認書作成・・隣接土地所有者と境界が確認されれば、境界標と呼ばれる目印を現地に設置します。その後、筆界確認書と呼ばれる境界確認文章2通作成し双方が1通づつ保管することになります。
尚、境界確定測量は、隣接土地所有者や道路管理者(官公署)との立会や、調査・測量図面作成等に約3ヶ月の期間を要します。
簡単ではありますが、以上が境界確定測量の流れになります。
境界確定測量は、時間・金銭ともに多くかかってしまいますが、将来起こりうるかもしれない紛争を防止する意味でも、出来る限り境界確定測量を行っていくことをお勧めします。
みなさん、こんにちは。
ひかり土地家屋調査士法人の吉村です。
今回は、土地の「越境物」についてお話したいと思います。
隣地さんとの敷地の境界を確認して欲しいといった依頼があります。
これは、土地の境界の事で隣地の方とトラブルがあるのと同じように、越境している構造物(屋根やブロック塀)や、樹木、引き込みしている電線等など、越境している建物があれば、隣地さんとのトラブルの原因となってしまいますので、そういったことを確認したいというような場合にご依頼を頂きます。
越境している構造物であったとしても、所有権は隣の人のものですから、勝手に壊したりすることはできません。
また、自分の建物が越境しているような場合には、「越境している瓦が落ちてくると危ないからすぐに取壊してほしい」や「越境している樹木からでる落葉が迷惑だからすぐに剪定してほしい」などの無理難題を言われることもあります。
このように、越境しているような建物などを放っておくことは、後々のトラブルの原因となりますから、思い立ったときに、越境の事実を確認しておく事が大切です。
隣地さんと越境物の確認ができれば、土地の所有者同士でお互いの認識を合意したことを証明する「覚書、確認書、協定書」を取り交しておけば、後々のトラブルを回避する事ができ、不動産を売却するとき、あるいは相続が発生して世代が交代したような場合でも、問題を先送りするようなことにはなりません。
ひかり土地家屋調査士法人では約20メートルほどの上空にある構造物や地中にある根っこまで、最新の測量機械を使用し、長年の経験に基づく測量技術を駆使し、越境物の確認をすることができます。
土地の越境などでラブルにならないように、隣地さんとの越境物について困っている、土地や建物に対しての不安事がある場合はいつでもお気軽にご相談頂ければと思います。
みなさん、こんにちは。
ひかり司法書士法人の冨永です。
問合せを受けることが多い、不動産を売却したときの譲渡所得税について簡単にご説明したいと思います。
不動産の譲渡所得税とは、「購入した金額(取得費)より、売却したときの金額が高くなる場合の利益に対して課税される税金」のことになります。
5,000万円(売却価額)-3,000万円(取得費)=2,000万円(利益)
2,000万円(利益)×20.315%=4,063,000円(長期所有の場合の所得税、住民税)
上記は一般的な事例ですが、居住用財産(自宅等)の譲渡であれば、特別控除の特例などがあり、税金が課税されない事例も多くあります。
よく相談を受けるのが、相続した不動産を売却した場合、つまり相談者本人が実際に住んでいない実家を売却した場合です。父親が不動産を購入しているため売買契約書が残っておらず、取得費がいくらかわからないような場合には、少し問題が発生してしまいます。
例をあげて説明しますと
父親が死亡し、その父親の自宅を相続人が相続して3,000万円で売却した場合。
(相続に関する特例や譲渡に係る諸費用は考慮していません)
購入時の売買契約書が見つからないだけで、これだけの税金負担になるのは非常に酷ですよね。
そういった場合、取得費を「市街地価格指数」で算出することにより税金が安くなる場合があります。
市街地価格指数とは、一般財団法人日本不動産研究所が、全国の地価を調査し、指数化しているものです。
この指数というのは、現在3,000万円で売ったということは、購入時の時点ならいくらで買ったであろうという金額を合理的に計算するための指数になります。
実際に、この市街地価格指数を利用して取得費を合理的に見積もり、税金の申告を行うことによって、取得費を5%とするよりも税金が低くなった事例もございましたので、購入時の売買契約書がない場合もあきらめずに専門家にご相談いただくと、税金が下がることもあるかもしれません。
全ての事例において市街地価格指数を利用することができるわけではなく、不動産の場所や取得時期等によっても制限されますので、その点はご注意くださいますようお願いいたします。
【相続】 不動産名義変更の必要書類
遺産分割協議書によって名義変更の手続きをする場合
| 必要な書類 | 必要な理由 |
|---|---|
| 亡くなられた方(以下、被相続人)戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍等 | 被相続人の出生から死亡までの記載のあるものが必要になります。こちらの書類を揃えることで、被相続人の相続人を確定することができます。
通常は、被相続人の最後の本籍地を管轄する役所に請求して、そこから遡っていくことになります。戸籍は法改正があったり、転籍していたり、また、婚姻、分家、家督相続など様々な原因で |
| 被相続人の住民票の除票か戸籍の附表の除票 | 被相続人の登記簿上の住所が最後の本籍地と異なる場合に必要になり、この書類によって被相続人の所有する不動産であることを証明します。 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続人は生存していることが必要ですので、こちらでそのことを証明します。 |
| 遺産分割協議書 | 誰がこの不動産を相続したのかなどを決めた書類になります。 |
| 不動産を相続する人の住民票 | 不動産の名義を受ける人は必要になります。こちらに記載されている住所と氏名が不動産の登記簿に記載され、その人の者であることが証明されます。 |
| 不動産を相続する人の委任状 | 司法書士に対する委任状が必要になります。 |
| 不動産の固定資産税評価証明書 | 法務局へ納める登録免許税を算出するのに必要となります。 |
遺言によって名義変更の手続きをする場合
| 必要な書類 | 必要な理由 |
|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本か除籍謄本 | 被相続人が亡くなられた事を証明するために必要になります。 |
| 被相続人の住民票の除票か戸籍の附表の除票 | 被相続人の登記簿上の住所が最後の本籍地と異なる場合に必要になり、この書類によって被相続人の所有する不動産であることを証明します。 |
| 遺言によって相続する人の戸籍謄本 | 相続人は生存していることが必要ですので、こちらでそのことを証明します。 |
| 遺言書 | 誰がこの不動産を相続したのかなどを確認するために |
| 不動産を相続する人の住民票 | 不動産の名義を受ける人は必要になります。こちらに記載されている住所と氏名が不動産の登記簿に記載され、その人の者であることが証明されます。 |
| 不動産を相続する人の委任状 | 司法書士に対する委任状が必要になります。 |
| 不動産の固定資産税評価証明書 | 法務局へ納める登録免許税を算出するのに必要となります。 |