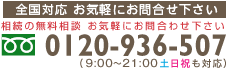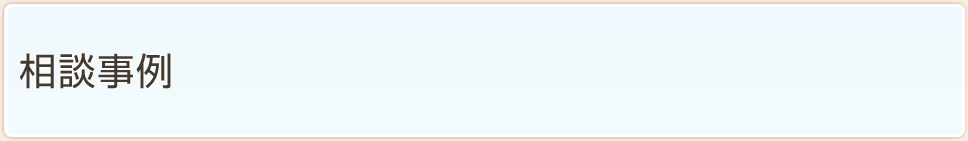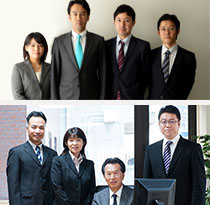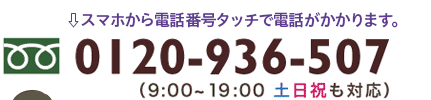こんにちは、測量部の道中です。
よくひかり測量設計の事務所には、下記のような問い合わせがよくあります。
『金融機関から融資を受けたいと考えているが銀行の担当者からあなたの自宅の一部が未登記である為、登記をしなければ融資を実行することが出来ないと言われた。どうすればいいですか?』というものですが『もちろん登記しないといけないですね』と答えます。
実際に、建物にもいろいろあり、登記できるかどうかは不動産登記法上の『建物』として認定されるかどうかで決まってきます。
たとえばビニールハウスやキャンピングカー式ハウスなどは登記できません。
登記の対象となる『建物』の要件とは次のようなものがあります。
- 屋根及び壁などで外気を分断していること(外気分断性あり)
- 土地に当該建物が固定され、容易に移動できないこと又、永続的に使用でできること(定着性あり及び永続性あり)
- 当該建物の目的とする用途に使用できる状態にあること(用途性、人貨滞留性あり)
- その建物自体が『不動産』として取引されることに値するものであること(取引性あり)
実際に対象の建物を確認してみるとコンクリートブロックの上に設置された組み立て式の物置などであった場合には定着性があるとは言えず登記できません。また、工事現場に設置されているようなプレハブの事務所であり、容易に移動できるものは永続性があるとは言えず登記できません。
このような場合には金融機関の担当者は登記ができない証明書等を求めてくることもあるようですが上記以外で建物として登記できるものに関しては登記すべきです。
不動産登記法上『建物』はその完成(新築時)より1ヶ月以内の建物表示が義務付けられています。

2016年度(平成28年度)税制改正大綱で、相続した空き家を売却した場合の所得税の軽減措置が新しく創設されました。いわゆる「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。
従来の「譲渡所得の3,000万円の特別控除」は、所有者自身が生活の拠点として利用していた家屋の売却が条件となっておりましたが、2016年4月からは、相続した空き家を売却する場合でも、3,000万円の特別控除の特例が適用されることになります。
しかし、この特例を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
- そのまま譲渡する家屋、又は当該家屋とともに譲渡する土地等
- 相続時から譲渡時までに、事業用、貸付用、又は居住用に供されていたことがないこと。
- 譲渡時において一定の耐震基準を満たしていること。
- 家屋を除却した後に譲渡される、その敷地の用に供されていた土地等
- 除却した家屋は、相続時から除却時までに、事業用、貸付用、又は居住用に供されていたことがないこと。
- 家屋除却後更地となった土地等は、相続時から譲渡時までに、事業用、貸付用、又は居住用に供されていたことがないこと。
※ただし、当該相続の時から当該相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとし、当該譲渡の対価の額が1億円を超えるものを除きます。(出典:平成28年度税制改正大綱より)
以上のように細かい条件がありますが、簡潔に述べると、1.相続した旧耐震基準の家屋を、耐震改修して売却するか、2.解体し更地にして売却する場合に、譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例が適用されるというものです。
政府としては「危険な空き家を減らすことに貢献すれば、減税しましょう」という考え方の様です。現実的には多額の代金がかかる耐震基準を満たす工事を行うよりも家屋を解体し更地にして売却する方が費用的には安く済むのではないかと思われます。(自治体によっては耐震工事の補助金制度があるそうですが。)
現在、相続された財産で居住されていない不動産を所有されている方は上記の制度を利用されてはいかがでしょうか。
関連記事:空き家の処分と管理などについて
今回は戸籍の集め方について少し書いてみたいと思います。
戸籍とはよく耳にするけど、いまいちどんなものかわからないという方は多いのではないでしょうか?
相続が発生すると不動産登記の名義変更はもちろんのこと預貯金の解約や、車や株式などの名義変更の手続きが必要になります。
そのほとんどの手続きに戸籍の添付が必要になります。これは被相続人が亡くなったこと及び被相続人の法定相続人がだれなのかを確定させるために必要になります。
しかしながら一般の方で戸籍を目にする機会というのは少ないのではないでしょうか。特に最近は免許証に本籍地が載らなくなったこともあり被相続人やご自身の本籍地がどこかわからないということも少なくありません。本籍地がわからない場合は住所地で住民票をあげれば本籍地が記載されます。
まず相続に必要な戸籍とは、被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍・除籍・原戸籍及び相続人の戸籍になります。
戸籍の中にも戸籍・除籍・原戸籍といった種類があります。
相続において戸籍を集めるとはこれら全ての種類を指していることが多いです。
まず戸籍とは、各個人の家族的身分関係を明らかにするために記載される公文書であり、夫婦とその未婚の子で編成され、各人の氏名・生年月日、相互の続柄(つづきがら)などを記載し、本籍地の市町村に置かれているものをいいます。
除籍とは、死亡、結婚、転籍などで戸籍が空白になったものを言います。例えば夫婦と未婚の子が一人の戸籍があり、父が死亡し、子が結婚し、その後に母が死亡した場合、母が死亡した時にその戸籍には誰もいなくなるので、除籍となります。
原戸籍とは、「はらこせき」「げんこせき」と読みます。改正原戸籍と言ったりしますが、過去に何度か戸籍の改正があり、そのときそのときに、それぞれ新たな様式や記載方法によって、戸籍が新しくされてきており、その新しくされる前の戸籍のことを原戸籍といいます。つまり戸籍の様式が変わり、新たに戸籍を作り直したときの作り直す今までの戸籍のことを原戸籍といいます。
ちなみにもう一つ戸籍の附票と呼ばれるものもあります。これは、戸籍には住所が記載されていないので、戸籍をとっても住所とのつながりはわかりません。戸籍と住所をつないでいるのが戸籍の附票となります。戸籍の附票は戸籍と同じく本籍地を管轄する役所でしか取得することは出来ませんが、その本籍地にいる間の住所の変遷が書いてあるので、何回も引っ越ししていて住民票では住所のつながりをつけることが出来ない場合に使われることもあります。